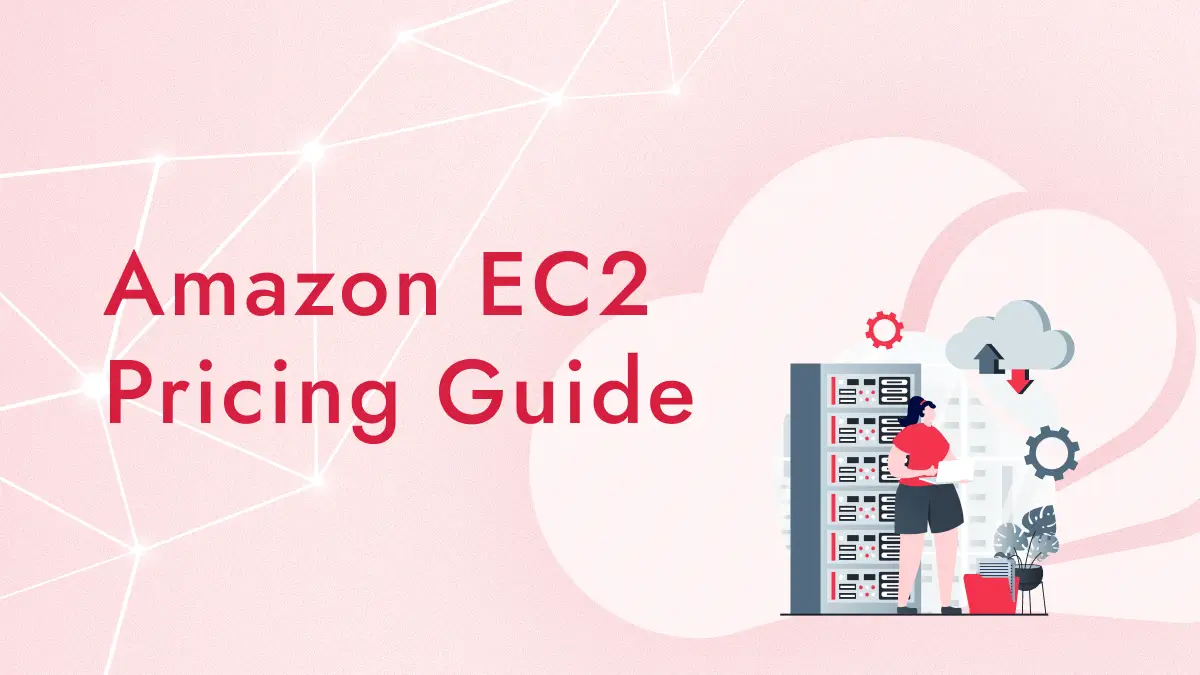
- Amazon EC2

AWS Direct Connectは、AWSクラウドと自社ネットワーク間を専用線で接続するサービスです。本記事では、その仕組みや構成例、VPNとの違い、導入時のメリット・料金目安まで、企業ネットワーク担当者が押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。
AWSと自社ネットワークを専用線で直接接続する「AWS Direct Connect」は、通信の安定性・セキュリティ・帯域確保を重視するユースケースで利用されるサービスです。
AWS Direct Connectは、AWSとオンプレミス環境を専用線で接続するためのサービスです。インターネットを経由せずに通信できるため、VPN接続などに比べて低遅延かつ安定したネットワークを構築できます。
主な特徴
専用線接続(1Gbps〜100Gbps)による帯域の確保
閉域網通信によるセキュリティの向上
帯域保証による業務影響の低減
冗長構成(HA構成)による可用性向上
Direct Connect Gatewayの活用により、複数リージョン・複数VPCとの接続にも対応
インターネット経由のVPNとは異なり、企業ネットワークとAWSを常時安定して接続するためのインフラ要素として設計されています。
Direct Connectが選ばれるのは、以下のような要件があるケースです。
業務システムのAWS移行
社内ネットワークとクラウドを常時安定接続する必要がある場合
大容量データの定期転送
映像データ、IoTログ、バックアップデータなどを高速・高品質に送信する場面
セキュリティ要件が厳しい業種
インターネット経由の通信が許可されない金融機関、公共機関、医療機関など
ディザスタリカバリ(DR)対策
異なるリージョン・データセンター間でのデータ同期やレプリケーション用途
ハイブリッドクラウド構成
オンプレとAWSでシステムが分散しており、恒常的な連携が必要な構成
Direct Connectは、物理的な専用線を通じてAWSとオンプレミス環境を接続します。
構成の基本は「オンプレミス環境 → データセンター内の接続ポイント → AWSリージョン内のVPC」という経路です。VPNと異なり、インターネットを通らずにAWSと直接通信できるため、帯域の安定性やセキュリティ要件を満たしやすい点が特徴です。
Direct Connectの接続イメージは以下のようになります。
[オンプレミス環境]
│
(ルータ/スイッチ)
│
専用線(1Gbps〜)
│
[AWS Direct Connectロケーション]
│
AWSネットワーク
│
[VPC]
構成上、ユーザー拠点とAWSの間に「Direct Connectロケーション(接続ポイント)」が存在します。これはAWSとネットワーク事業者が接続する共用施設で、多くの場合、キャリアやクラウドエクスチェンジ事業者が提供します。
物理構成としては、以下の3点が主な要素です。
オンプレ側のネットワーク機器:ルーター、スイッチ等。BGPを使ってAWSとのルーティングを確立する
通信事業者による回線提供:Direct Connectロケーションまでの物理回線
AWS側の仮想インターフェース:VPCなどと接続する論理的なインターフェース
専用線の終端はAWSが指定する接続ポイント(Direct Connectロケーション)で、そこからAWSのネットワークに接続されます。ロケーションとVPC間の構成には「Virtual Interface(VIF)」を使います。プライベートVIFが一般的ですが、状況に応じてパブリックVIFやTransit VIFを選択します。
Direct Connectは要件に応じて複数の接続構成を選択できます。代表的な2パターンとして、「単一接続/冗長構成」と「パートナー接続」の違いを整理します。
単一接続は、Direct Connect回線を1本だけ利用するシンプルな構成です。構築やコストの面で導入しやすい反面、物理障害・ネットワーク断の際に通信が完全に停止するリスクがあります。
一方、冗長構成(High Availability:HA構成)では、2つの独立した回線を異なるルートで引き、フェイルオーバーに対応できるようにします。AWSは本番利用において冗長構成の導入を推奨しています。
一般的な構成
異なるDirect Connectロケーションに接続
異なるデバイス(AWS側の接続ポイント)への分散
BGPを用いたルート制御によるフェイルオーバー対応
通信の可用性やSLAが求められるシステムでは、単一接続はリスクが高く、冗長構成が事実上の前提となります。
自社でDirect Connectロケーションに物理的に接続するのが難しい場合は、AWS Direct Connectパートナーを経由する方法が有効です。
この構成では、AWSが認定したネットワークプロバイダのインフラを通じて、自社拠点とAWSを間接的に接続します。
主な特徴
専用線の手配や構成設計をパートナーが代行
短期間かつ比較的低コストで導入可能
物理接続はパートナー拠点 → Direct Connectロケーション
中規模以下の企業や、複数拠点を持つ企業でスピード感を持って導入したい場合に適した選択肢です。
Direct Connect Gateway(以降、DXGW)は、AWS Direct Connectと複数のVPCやリージョンを論理的に接続するための中継的なサービスです。Direct Connect回線と複数のVPC間の接続をシンプルに管理し、より柔軟なネットワーク設計を可能にします。
通常、Direct Connectは1つのVPCと直接接続する構成が基本です。しかし、複数リージョン・複数VPCとの接続が必要な場合、個別に構成を組むと設計が複雑になります。
Direct Connect Gatewayは、以下の役割を担います。
複数VPCへの接続を集約
1つのDXGWに複数のVPCを関連付けることで、回線の集約と接続管理の簡素化が可能
リージョンをまたぐ接続に対応
複数リージョンに存在するVPCとも接続可能(例:東京リージョンからオレゴンリージョンのVPCへ接続)
Transit Gatewayとの併用も可能
大規模ネットワーク構成にも柔軟に対応できる設計が可能
企業のネットワーク構成が拡張・多様化しても、Direct Connect回線の活用効率を保ちつつ柔軟な運用が可能になります。
特にグローバル企業や複数AWSリージョンを活用する構成で有効です。以下のようなシナリオに適しています。
日本拠点から複数リージョンのAWS環境へ接続
東京リージョンとシンガポール/バージニアなどを1つの専用線で接続
本社と各海外拠点を一括でAWSに接続
各拠点のネットワーク設計を単純化し、DXGWで一元管理
リージョン横断のデータ同期やバックアップ
DXGW経由で安全かつ安定した転送経路を確保可能
こうしたケースでは、回線コスト・構成管理の負荷を抑えつつ、広域ネットワークの安定運用が実現できます。
Direct Connect Gateway(DXGW)に加えてAWS Transit Gateway(TGW)を組み合わせることで、VPCやオンプレミス環境を集約的かつ効率的に接続できる構成が実現します。拠点数やVPC数が多い場合、この組み合わせはネットワーク設計の簡素化と可用性の向上に寄与します。
Transit Gatewayは、AWS内に複数あるVPC、VPN、Direct Connect Gatewayなどをハブ&スポーク型で接続するルーティング基盤です。
主な役割とメリット
複数VPC間のルーティングを集約
各VPCを直接接続する個別の設定が不要になり、設計・運用が簡素化される
VPNやDirect Connectなど異なる接続方式を統合
ハイブリッド構成でも一元管理が可能
スケーラブルで高可用なアーキテクチャ
リージョン単位で複数のアタッチメントを冗長構成にできる
クロスアカウント連携にも対応
複数アカウントで構成されたAWS環境でも利用可能
典型的な構成は以下の通りです。
[オンプレミス環境]
│
Direct Connect回線
│
[AWS Direct Connect Gateway]
│
[AWS Transit Gateway]
├───── VPC-A(東京)
├───── VPC-B(大阪)
└───── VPC-C(別アカウント)
この構成では、Direct Connect Gatewayを介してAWS環境に物理接続し、Transit Gatewayで複数のVPCにルーティングを分配します。Direct Connect Gatewayが物理回線の集約ポイント、Transit GatewayがVPC接続の中継ポイントとして機能する構造です。
組み合わせ構成の設計では、以下の点に注意が必要です。
Transit Gatewayはリージョン単位での設計
DXGW経由で接続可能だが、各TGWはリージョンごとに作成される
ルーティングの分離と集約を意識
VPCごとの通信要件に応じたルートテーブル設計が必要
BGPルーティングの整理
冗長構成の場合、アクティブ/スタンバイ設計や、メトリック調整が必要になる
通信制御のガバナンス設計
TGWの共有やクロスアカウント接続時はIAM・セキュリティポリシーも含めた設計が求められる
この構成は、Direct Connectのメリット(高帯域・安定性)を維持しながら、拡張性と管理性を確保するための実践的な選択肢となります。
AWSとオンプレミス環境を接続する手段としては、Direct ConnectのほかにVPNも選択肢となります。通信経路、帯域、セキュリティ、コストの4つの観点から両者の違いを整理します。
VPNとDirect Connectでは、通信経路の構造が根本的に異なり、それが通信品質に直接影響します。
AWS VPNは、インターネットを経由してオンプレミスとAWSを接続する方式です。IPsecトンネルを使って暗号化通信を行うため、一定のセキュリティは確保されますが、経路がインターネット任せになるため、以下の課題が生じる可能性があります。
通信遅延の変動が大きい
時間帯や経路状況によりレイテンシが不安定になることがある
ネットワーク断の影響を受けやすい
ISPや外部ネットワークの障害によりアクセス不能になるリスクがある
回線品質の保証がない(ベストエフォート)
VPNは初期導入の手軽さや低コストが利点である一方、高い可用性や品質が求められるシステムには不向きです。
Direct Connectは、通信事業者が提供する物理的な専用線を利用し、オンプレミス環境とAWS間を閉域ネットワークで直接接続します。インターネットを経由しないため、以下のメリットがあります。
通信経路が固定され、安定性が高い
レイテンシが低く、変動が少ない
インターネット障害の影響を受けない
専用帯域により通信品質が予測可能
基幹系システムや大容量データの転送など、品質が業務に直結する用途に適した接続方式です。
接続方式を選定するうえで、通信帯域の安定性とスループット性能は重要な判断基準となります。ここではVPNとDirect Connectの帯域に関する違いを整理します。
VPNはインターネットを経由するため、帯域は保証されず、利用状況により変動します。
特性
ISPや経路の混雑状況に影響を受ける
時間帯によって通信速度や応答性にばらつきが出る
安定したスループットが求められる用途には不向き
大量データの連続転送や映像配信、リアルタイム性が求められる処理では通信の揺らぎが問題になる
トラブル時の原因特定が難しい
公共インフラを利用するため、トラブル時にどの経路で発生しているか特定しにくい
可用性やスループットに強い要件がない業務では十分対応可能ですが、継続的な転送性能が重視される場面には向いていません。
Direct Connectは物理専用線を使用するため、明確な帯域プラン(1Gbps/10Gbps/100Gbps)を選択でき、通信性能が予測可能です。
主なメリット
契約帯域に応じた安定したスループットを確保
ピーク時でも通信速度が落ちにくい
帯域使用状況をモニタリング可能(CloudWatch Metrics連携)
回線が物理的に分離されているため、他ユーザーの影響を受けず、トラフィック品質を安定的に維持できます。ミッションクリティカルなアプリケーションや、大容量の定期転送を行う業務に適しています。
セキュリティ要件は接続方式選定において重要な判断軸のひとつです。VPNとDirect Connectでは、通信経路の性質やリスクの前提が異なります。
VPNは、IPsecによる通信の暗号化を前提としたセキュアな接続方式です。インターネット経由でも盗聴や改ざんのリスクを防げるよう設計されていますが、以下の前提で運用されます。
通信内容は暗号化されているが、経路は公共ネットワーク
攻撃対象となる経路を完全に排除できない
セキュリティポリシーに制約がある業種では非推奨
金融・医療・公共機関などでは「インターネット非経由」が求められるケースがある
VPNは一般的な業務用途には十分対応可能なセキュリティレベルですが、インフラレベルでの閉域性は担保されません。
Direct Connectは、インターネットを通らない閉域網での通信が可能です。通信内容の暗号化はオプションとなるものの、経路そのものが閉じているため、以下のメリットがあります。
通信経路がインターネットから完全に分離されている
トラフィックが第三者の影響を受けにくく、攻撃対象にもなりにくい
業種別ガイドラインや法規制に準拠しやすい
暗号化が必要な場合には、Direct Connect上にVPN over Direct Connectを構成することも可能です。
VPNとDirect Connectでは、導入にかかるコストと工数に大きな差があります。それぞれの特性を踏まえた上で、自社の要件やリソースに応じた選定が必要です。
VPNは、AWS側でのVPN Gateway作成とオンプレミス側の機器設定のみで利用可能なため、Direct Connectに比べて低コストかつ短納期で構築できます。
特徴
AWS側の課金は固定費+転送量課金のみ
物理回線の手配が不要なため、数日〜短期間で導入可能
テスト用途や短期プロジェクトでも使いやすい
オンプレ機器の対応(IPsec/BGPなど)によっては運用が簡略化される
コストと柔軟性の面では優れており、小規模環境や冗長経路のバックアップ回線としても有効です。
Direct Connectは、通信事業者による専用線手配が必要であり、構築に時間とコストがかかります。
特徴
初期費用:専用線敷設やクロスコネクト工事費用が発生
月額費用:ポート料金+データ転送料金+(必要に応じて)パートナー利用料
導入リードタイム:1〜2か月程度かかるケースが多い
構成・設計:BGPや冗長化構成の設計が必要
ただし、これらのコストに見合う通信品質・帯域安定性・可用性の高さがあり、本番環境や基幹系システムには適した選択肢です。
Direct Connectは、コストや導入工数は一定かかるものの、それに見合った性能・安定性・セキュリティ上のメリットがあります。導入によって得られる代表的な利点と、導入が適しているユースケースを整理します。
Direct Connectの導入によって得られるメリットは、通信帯域の安定化、セキュリティ要件の確保、大容量データ通信への最適化などが挙げられます。
専用線を利用するため、契約帯域に基づいた安定した通信が可能です。特に以下の点でVPNより優れています。
ピーク時でも安定した通信速度を維持
レイテンシの変動が小さく、業務処理への影響が少ない
BGPによる経路制御により、意図した経路での安定運用が可能
通信品質が安定しないことによるアプリケーションのパフォーマンス劣化や、バッチ処理の遅延などを回避できます。
インターネットを経由しない閉域網構成により、以下のセキュリティ上の利点があります。
セキュリティ要件が厳しい業界(金融・医療・公共)にも対応
通信経路そのものが隔離されており、設計上の信頼性が高い
要件次第では、閉域接続+暗号化(VPN over Direct Connect)による多層的な対策も可能です。
高帯域・安定性・低遅延の3点により、大量データの移動や定期的なレプリケーションに最適です。
業務システムのログやバックアップデータの定期転送
災害対策としての遠隔リージョン間データレプリケーション
大容量の映像・音声・メディアデータのリアルタイム処理
通常のインターネット経由では処理しきれないレベルのデータ通信でも、品質を維持した運用が可能です。
Direct Connectは、すべてのAWS利用企業に必須というわけではありません。ただし、特定の要件や業種においては、他の接続方式では代替しにくい利点があります。
業務システムや社内基幹システムをAWSへ移行する場合、通信の安定性・低遅延・高可用性が必須です。Direct Connectはこれらの要件を満たすため、以下の環境で選ばれます。
オンプレミスのデータベースとAWS上のシステムが連携する構成
ユーザー操作の応答速度が業務品質に直結するシステム
24時間365日安定稼働が求められる業務基盤
既存のオンプレミスデータセンターとAWSを接続し、ハイブリッドクラウド構成を取る場合に適しています。
オンプレとAWSで負荷分散/バックアップを行う構成
ADやファイルサーバー等の連携を前提とする社内インフラ
オンプレDCとAWS間での非断絶型システム移行
このようなケースでは、継続的な通信品質が求められるため、VPNよりもDirect Connectが適しています。
映像・音声・3Dデータなどの大容量ファイルのリアルタイム送受信や処理が業務に含まれる場合、安定した広帯域接続が必要です。
放送局・制作会社によるAWSへの動画素材のアップロード
配信サービスにおける高解像度映像の転送と処理
CG/VFX制作工程でのAWS側クラウドレンダリング処理
このような業界では、通信の一時的な乱れでも業務影響が大きいため、Direct Connectによる安定接続が必須に近い要件となります。
金融・医療・公共といった規制の厳しい業種では、「インターネットを経由しない閉域接続」がセキュリティ要件として求められることがあります。
FISC、NISC等のガイドラインに準拠した通信経路が必要
外部通信経路のリスクを極小化する必要がある
顧客データや機微情報の扱いに法的制約がある
Direct Connectはこれらの要件に対応可能な構成を取りやすく、第三者審査・監査にも耐えうるインフラ設計を実現できます。
Direct Connectの料金は、単純な月額固定制ではなく、ポート使用料・データ転送量・回線事業者の費用など複数の要素で構成されます。基本的な料金構成と、利用規模ごとのコスト目安を整理します。
AWSの標準サービスと異なり、複数のコスト要素から構成されます。導入検討時には、構成に応じて以下の費用が発生する点を把握しておく必要があります。
AWS側で提供されるDirect Connectポートに対して、帯域ごとに固定の月額料金が発生します。主な料金体系は以下の通りです。(東京リージョンの場合の一例)
帯域幅 | 月額ポート料金(参考)1 USD = 150 JPY(概算) |
1Gbps | 約 $200〜$270 |
10Gbps | 約 $1,670〜$2,000 |
100Gbps | ※要問い合わせ(制限あり) |
※料金はリージョン・通貨レート・提供条件により異なるため、最新情報は公式料金ページを参照してください。
AWSからオンプレミスへのアウトバウンド通信(送信)には、転送量に応じた料金が発生します。インバウンド通信(受信)は無料です。※参考値(東京リージョン)
最初の 10TB:$0.0491/GB
10〜50TB:$0.0480/GB
50TB超:$0.0469/GB
大量データを送信する構成では、この転送料金が月額コストに大きく影響します。
自社からDirect Connectロケーションまでの物理回線をAWS認定パートナーに委託する場合、その事業者側で別途費用が発生します。
料金の特徴
月額料金は約 $270〜$1,000が一般的
提供エリア、帯域、冗長構成の有無によって変動
導入初期に工事費・設定費が必要な場合あり
AWS側には請求されず、ネットワーク事業者との直接契約・支払いになります。特に複数拠点で利用する場合は、拠点数に比例してコストが加算されます。
想定される利用規模ごとにDirect Connectの月額費用の目安をシミュレーションします。実際の料金は回線事業者や構成、使用量により異なるため、あくまで検討初期の参考値としてください。
想定シナリオ:拠点1カ所、バックアップや検証環境との通信が中心。パートナー回線を利用し、1Gbps帯域で単一接続。
✔ VPNより高コストだが、定期バックアップや閉域網要件がある場合の選択肢として現実的。
想定シナリオ:複数VPCと接続した業務システム、10TB/月前後のデータ送信あり。冗長構成(1Gbps ×2)+Direct Connect Gateway構成。
✔ 業務システムや社内基盤のクラウド連携に耐えうる設計で、コストに見合った安定性を確保。
想定シナリオ:映像配信・大量データ処理・DR構成など。10Gbps以上の広帯域+Transit Gateway+複数拠点接続。
✔ 大規模運用前提の安定性とスループットが要求される業種・用途向けの構成。
Direct Connectの導入にあたっては、回線手配や設計上の制約、可用性確保の観点で事前に検討すべきポイントがあります。このセクションでは、導入時によくある課題と注意点を整理します。
Direct Connectは、インターネット経由で即時利用できるVPNと異なり、物理回線の調達や設定が必要になるため、導入までに一定の期間を要します。
以下のような要因により、リードタイムが1〜2か月以上かかるケースもあります。
通信事業者による専用線手配・工事(拠点の立地や設備状況により調整が必要)
AWS接続ポイント(ロケーション)の空き状況(ポート逼迫による待機)
クロスコネクト(DC内の物理接続)の調整
社内稟議、セキュリティレビュー、BGP設計などの調整工程
導入スケジュールを検討する際は、検証や接続テストも含め、「最低でも1か月以上」のリードタイムを見込んだ計画が必要です。
Direct Connectは単一接続でも利用可能ですが、物理障害・ネットワーク障害が発生した場合に通信が完全に途絶えるというリスクがあります。本番環境や基幹系システムにおいては、単一構成は推奨されません。
AWSでは、本番用途での利用時に異なるロケーションやデバイスへの2系統接続(冗長構成)を推奨しています。代表的な冗長構成の考え方は以下の通りです。
2本の独立したDirect Connect回線を確保する
異なるロケーションやAWS側の接続デバイスを使用する
BGPでのアクティブ/スタンバイ構成、またはアクティブ/アクティブ構成を設計する
片系で障害やメンテナンスが発生しても、通信の継続性と業務の可用性を確保できます。クラウド接続を前提とした設計を行う場合、冗長化はコストではなく保険と捉えるべき設計要件です。
Direct Connectの導入にあたっては、AWS側とオンプレミス側のネットワーク設計が適切に連携している必要があります。考慮すべき技術的観点を2つに分けて解説します。
Direct Connectでは、AWSとオンプレミス間のルーティングにBGP(Border Gateway Protocol)を使用します。冗長構成やフェイルオーバー設計を行う場合、以下の点に注意が必要です。
アクティブ/アクティブ接続時の帯域配分と経路選定
アクティブ/スタンバイ構成時のメトリック設定による優先制御
想定通信量に基づいた帯域設計(1Gbps/10Gbps)
CloudWatchを使ったトラフィックの可視化と監視設計
BGPの設計次第で冗長性やパフォーマンスに大きく差が出るため、事前の通信要件の洗い出しとパス制御ポリシーの明確化が不可欠です。
Direct ConnectはVPCと直接接続するのではなく、仮想インターフェース(VIF)を経由し、VPCと接続されます。以下の点に注意が必要です。
プライベートVIF/パブリックVIF/Transit VIFの選定
VPCとVGW(仮想プライベートゲートウェイ)またはTGW(Transit Gateway)の関連付け
複数VPCをまたぐ場合のルートテーブル整合性
セキュリティグループやNACLの設定漏れによる通信不可リスク
設計の整合が取れていないと、接続は成功していても通信が通らない、といったケースが多く見られます。Direct Connectだけでなく、VPC側の設計も含めた一体の構成管理が重要です。
AWS の使い方、見積もり、構成、運用などで迷いや不安がある場合は、お気軽にご相談ください。現地チームとの共通認識づくりや前提条件の整理から、判断をスムーズに進めるお手伝いをします。
本サービスは、日本で最初の商用インターネットサービスプロバイダーとして誕生した IIJ グループと、AWS プレミアティアサービスパートナーであるサーバーワークスが共同で提供する「IIJ Managed Cloud for AWS」です。東南アジアを含むグローバル環境での利用にも対応し、現場の判断に寄り添った AWS 支援を行っています。
▶ 詳しい資料を確認する
▶ AWS活用の相談をしてみる
