
- ベトナム
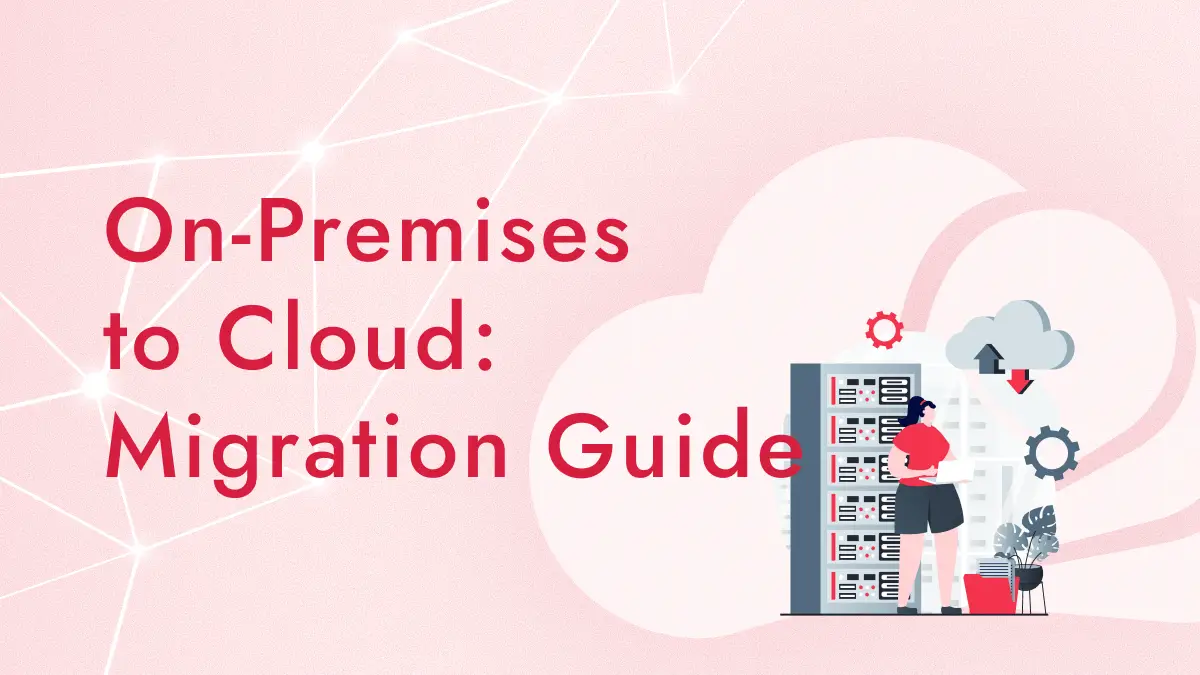
オンプレミス環境からAWSへのクラウド移行は、多くの企業が直面する重要なテーマです。しかし、何から手をつければよいのか、どのように進めれば失敗を避けられるのか悩むケースも多いでしょう。本記事では AWS移行の基本手順・構成設計の考え方・代表的な移行ツールの選び方 まで、初めての移行でも実践しやすい形で解説します。
オンプレミス環境からAWSへの移行は、多くの企業が直面する重要なテーマです。サーバやストレージ、ネットワーク機器を自社で保有して運用する従来型のオンプレミス環境から、AWSが提供するクラウド基盤へシステムを移行することで、コスト最適化、可用性向上、運用効率化など多くのメリットを得られます。
ただし、現行システムの構成や業務要件に応じて、移行方法や再設計の範囲は大きく異なります。ここでは、代表的な移行パターンとその特徴、移行によって得られる効果を解説します。
AWSへの移行パターンは大きく3つに分けられます。移行期間、コスト、クラウド化による効果を総合的に踏まえ、自社に合った方式を選ぶことが重要です。
既存サーバやアプリケーションをほぼそのままAWS上のEC2などに移行する方法です。構成変更を最小限に抑え、短期間でクラウド移行を実現できます。
メリット
迅速な移行が可能で、短期間でクラウド利用を開始できる
アプリの改修が不要なため初期コストを抑えやすい(軽微な修正が発生する場合あり)
デメリット
運用負荷やコスト構造がオンプレ時代と大きく変わらない
技術的負債をそのまま持ち込むリスクがある
適しているケース
ハードウェアの保守期限切れが迫っており、早急な移行が必要
検証期間が限られている
まずはAWSで稼働を開始し、後に段階的にモダナイズしたい
アプリ自体は大きく変更せず、周辺基盤をAWSのマネージドサービスに置き換える移行方式です。たとえば、DBをRDSへ、ファイルサーバをAmazon FSxやS3に移すなどが該当します。
メリット
運用負荷を大きく軽減できる
可用性・拡張性が向上し、クラウドの恩恵を部分的に享受できる
デメリット
検証や調整に一定の工数が必要
移行計画を慎重に進めないと、移行中にサービス停止リスクが高まる
適しているケース
運用保守に課題があり、マネージド化による効率化が急務
コスト最適化を中期的な目標としている
将来的にRe-architectを視野に入れた段階的なモダナイズを進めたい
アプリケーションをクラウドネイティブに再設計するアプローチです。マイクロサービス化やサーバレスアーキテクチャへの移行を伴います。
メリット
スケーラビリティや開発スピードを大幅に向上できる
運用の自動化・効率化を最大化できる
コスト最適化とビジネス価値創出に直結する
デメリット
設計・開発コストが高く、長期プロジェクトになりがち
高度なAWSスキルと体制が必要
適しているケース
既存システムの技術的負債が大きく再構築が必須
サービスを急速に成長させる必要がある
DevOps文化を前提にした組織変革を進めている
AWSへの移行は単なるサーバ引っ越しではなく、企業に多くの付加価値をもたらします。代表的なメリットは以下の通りです。
ハードウェア購入やデータセンター維持費といった固定費(CapEx)を変動費(OpEx)に転換できる
リソースを利用状況に応じて柔軟に増減可能
リザーブドインスタンスやセービングプランを活用したコスト最適化が容易
トラフィック急増や事業拡大に合わせて即時スケールアウト/スケールインが可能
海外リージョンを活用したグローバル展開がスムーズ
マルチAZ構成を標準化することで、システム障害時の影響を最小化
バックアップやDR(災害復旧)環境を低コストかつ短期間で構築可能
RDSやECS、Lambdaなどのマネージドサービスを活用することで、パッチ適用や障害対応など運用業務を軽減
CloudWatchやEventBridgeを用いた監視・自動化により、少人数運用も実現可能
オンプレミス環境からAWSへ移行する際は、準備 → 設計 → 実行 → 最適化という大きな流れで進めます。各ステップで必要なタスクを明確にしておくことで、計画的に移行を進められます。
AWS移行の成功は、初期段階での準備に左右されます。現状を正しく把握し、移行対象と優先順位を明確にすることが重要です。
既存システム、サーバ、アプリケーション、データベース、ストレージなどをリスト化
利用頻度や重要度、依存関係を整理
「移行する」「廃止する」「クラウドネイティブ化する」など、今後の方向性を分類
重要度やリスク、移行難易度を考慮して優先順位を決定
検証対象やPoC(概念実証)に適したシステムを選定
最初の移行範囲(スコープ)を明確化し、段階的に進める計画を策定
オンプレ環境のコストを可視化(ハード保守費、電力、運用人件費など)
AWS移行後のランニングコストを試算
投資対効果(ROI)や総所有コスト(TCO)を比較し、経営層への説明資料を作成
準備段階で得られた情報をもとに、AWS上での構成を設計し、移行計画を具体化します。
マルチアカウント戦略を前提に、Organizationsで統制管理を設計
アカウント分割、OU(組織単位)設計、ベースラインポリシーを定義
セキュリティ基盤や監査ログの集約設計も含めて計画
VPC設計、Direct ConnectやVPNの接続方式の決定
IAMポリシーやKMSによる暗号化設計
CloudWatchやCloudTrailを活用した運用監視体制の整備
本番移行前に、PoCやステージング環境を構築してテスト
想定トラブルやパフォーマンスを確認
移行ツールやスクリプトの動作確認もこの段階で実施
設計フェーズで固めた内容をもとに、実際にデータとシステムをAWSへ移行します。
AWS DataSyncやSnowballを用いた大量データ転送
DBはAWS Database Migration Service(DMS)で段階的に移行
移行中のデータ整合性を確認する仕組みを設置
AWS Application Migration Service(MGN)でVMをAWSへリフト&シフト
一部はコンテナ化やサーバレス化でリプラットフォームを実現
移行後はElastic Load Balancingなどで冗長化を確保
移行後の動作確認(性能・機能テスト、ユーザー受け入れテスト)
本番切り替え時は段階的なリリース(Blue/Green、カナリアリリース)を活用
実稼働後のモニタリング結果をもとに、リソースやコストを最適化
Auto Scalingやリザーブドインスタンスなどを導入して運用コストを削減
運用設計を継続的に改善し、クラウド運用文化を定着させる
オンプレミス環境からAWSへ移行する際は、クラウド移行特有の課題だけでなく、オンプレ環境ならではの制約やトラブルも多く発生します。この章では、移行プロジェクトで直面しやすい問題点と、その対策を実務視点で解説します。
H4 部署間の責任分界が不明確になりやすい
クラウド移行は、情シス・開発・運用・セキュリティ部門など複数部署が関与します。権限や責任範囲が曖昧なままだと、設定漏れや意思決定の遅延が発生しやすくなります。
対策例:
RACIチャートを使った役割分担表の作成
設計・承認フローを事前に合意
オンプレとAWSでは運用スタイルが異なるため、運用チームの役割重複や衝突が起きがちです。
対策例:
AWS運用の責任範囲を再定義
監視や運用ツールの統合を計画的に進行
特定のNICやUSBキーなどハードウェア依存が強いアプリは、そのままAWSへ移行できません。
対策例:
代替手段の検討(仮想デバイス、ライセンス方式変更)
Lift & Shiftでの再現が困難な場合はRe-platformを視野に入れる
Windows Server 2008や古いUNIXなど、AWSで非推奨のOSは移行前にアップグレードが必要です。
対策例:
OSアップデート計画を移行前フェーズで実施
ベンダーサポートの有無を確認
移行時はAWSとオンプレを安全に接続する必要があります。
VPN接続:短期間で構築できるが帯域が限られる
Direct Connect:大容量データ移行や本番接続向き
AWS側のセキュリティグループやACLとオンプレのファイアウォール設定が噛み合わないと、移行後に通信障害が発生します。
対策例:
事前にIPレンジやポート要件を一覧化
双方のネットワーク設計チームでレビュー
H4 NAS/SAN移行時の考慮事項
SMBやNFSのアクセス権限を維持したまま移行する必要がある
FSx for Windows/NFSなどAWSサービスへの置換を検討
数十TB以上のデータはAWS DataSyncでオンライン転送
数百TBクラスはAWS Snowballを活用した物理搬送が効率的
仮想化ソフトやAWS側ドライバとの非互換が発生するケース
AWS MGN利用時は最新バージョンへの更新を移行前に行う
MACアドレス固定前提で動作するライセンス管理システムは注意
AMI化や新規構築時にライセンス再設定が必要
移行予定のソフトがAWS対応ライセンスかを確認
ライセンスモデル変更が必要な場合はベンダーと早期に交渉
EC2専用ライセンス要件やサポート条件を満たす必要あり
監査対応のためライセンス証跡を管理
EventBridgeでのスケジュール実行
Step Functionsでワークフロー管理
AWS Batchやサードパーティ製ジョブ管理ツールも選択肢に
移行後のスケジュール動作確認
並列実行・リトライ処理の確認
監視・通知連携の検証
データ型やストアドプロシージャの互換性問題
外部接続アプリの接続文字列変更忘れ
パイロット移行:小規模DBで先行テスト
段階切替:本番稼働中のデータ同期を行い、最終切替でダウンタイムを最小化
短期的には既存監視を維持、長期的にはCloudWatchやManaged Grafanaへ移行
運用チームのスキルやコストを基準に判断
オンプレ・AWS双方のメトリクスを統合管理
ログはCloudWatch Logsへ一元集約
権限付与が場当たり的でセキュリティ事故発生
運用フローがオンプレ時代のまま硬直化
AWS認定資格やハンズオンを活用した体系的トレーニング
移行初期から「クラウド運用チーム」を立ち上げてナレッジ共有
オンプレミス環境からAWSへ移行する際は、単にサーバやデータをクラウドに移すだけでなく、ネットワーク・セキュリティ・可用性といった設計をクラウド向けに最適化する必要があります。この章では、AWS移行後の安定稼働を見据えた構成設計の考え方を解説します。
クラウド移行時のネットワークは、オンプレミスとの接続を維持しつつ、AWS上での柔軟な通信設計を実現することが重要です。
VPN接続
短期間で構築可能。初期コストを抑えられる
帯域は限られるため、検証や小規模移行に適している
AWS Direct Connect
専用線による高帯域・安定接続
大規模移行や本番運用に必須
AWS上のネットワーク基盤となるVPCを、移行前にしっかり設計
ポイント
アカウントやシステム単位でVPCを分割
セキュリティ要件に応じてパブリック/プライベートサブネットを適切に設計
VPC PeeringやTransit Gatewayによるネットワーク拡張を計画に含める
オンプレ時代のネットワークセグメントをそのまま移行せず、AWS向けに最適化
サブネットごとのCIDR計画を明確化
セキュリティグループ・NACL・ルートテーブルの関係を整理し、通信制御を多層で実施
クラウド移行後はセキュリティ管理の考え方がオンプレとは異なります。AWSが提供する機能を活用し、統制を自動化することが重要です。
IAMユーザー・ロール・ポリシーを活用し、最小権限で運用
SSO(AWS IAM Identity Center)による統合認証基盤を整備
権限付与ルールを事前に設計し、運用フローを定義
S3やEBSなどのストレージは暗号化をデフォルト有効化
CloudTrail・CloudWatch Logsを用いた監査ログ管理
KMS(Key Management Service)で鍵管理を統一
AWS Organizationsを活用し、アカウント統制を一元化
SCP(Service Control Policy)で利用サービスを制限
業界規制(PCI DSS、HIPAAなど)を満たす構成を事前に設計
クラウド移行後は「止まらないシステム」を前提に、障害時の切り替えや復旧計画を組み込みます。
マルチAZ構成
本番システムは必ず複数AZに分散配置
DBはAuroraやRDSのマルチAZ構成を標準採用
マルチリージョン構成
DR対策として別リージョンへのレプリケーションを検討
Route 53を使ったフェイルオーバー構成を設計
バックアップ対象:DB、S3、EBS、設定情報(IaC含む)
ポイント
バックアップポリシーは自動化(AWS Backup活用)
定期的なリストアテストを実施し、復旧時間(RTO)とデータ損失許容範囲(RPO)を確認
法令遵守に対応した保管期間と管理体制を設計
AWSへの移行をスムーズかつ安全に進めるためには、適切なツール選定が不可欠です。ここでは、AWS公式が提供するツールと、サードパーティ製ツールの代表例を紹介します。
AWSが提供するツールは、クラウド移行を前提に設計されており、サポート体制やサービス統合の面で安心感があります。
オンプレミスの物理サーバや仮想マシン(VMware、Hyper-Vなど)をAWSへリフト&シフトするための移行ツール。
特徴
本番環境に影響を与えずにリアルタイムレプリケーションを実行
ダウンタイムを最小化しながら移行可能
移行後はAWS上で検証後に本番切替が可能
用途
既存サーバ群をそのままクラウドへ移行したい場合に最適
オンプレや他クラウドのデータベースを、AWS上のRDSやAuroraに移行するためのサービス。
特徴
稼働中DBからの段階的移行に対応(ダウンタイムを最小化)
同種DB間だけでなく、異種DB間(Oracle → Auroraなど)の移行もサポート
用途
業務を止められないミッションクリティカルなDB移行に適している
オンプレミスとAWS間、またはAWSサービス間での大容量データ転送を自動化するツール。
特徴
SMB/NFS対応、ストレージ間の移行に強い
データ圧縮と暗号化により、安全かつ効率的に転送
用途
NASやファイルサーバの移行、S3やEFSへの大量データ転送
複数の移行プロジェクトを一元管理できるダッシュボード。
特徴
MGN、DMSなど複数ツールの進捗を可視化
プロジェクトごとに移行状況を追跡可能
用途
大規模移行プロジェクトで複数チームを統括する場合に便利
AWS公式ツールだけでは補えない領域は、サードパーティ製ツールを組み合わせることで解決します。
Veeam Backup & Replication
オンプレやAWSを含むマルチクラウド環境のデータ保護に対応
CloudEndure Migration(旧製品)
現在はAWS MGN(Application Migration Service)に統合されており、CloudEndure Migrationの利用は実質的にない
New Relic
AWSとオンプレを含むシステム全体の監視を一元管理できる
アプリケーションのパフォーマンス可視化やアラート管理にも対応
Terraform / Ansible
IaC(Infrastructure as Code)を活用した構成管理や移行自動化に有効
AWS移行プロジェクトは、計画通りに進めたつもりでも思わぬ落とし穴に陥るケースが少なくありません。ここでは、よくある失敗パターンと、その防止策を解説します。
AWS移行プロジェクトでは、初期準備が不十分だとスケジュールが後ろ倒しになり、コスト増加や関係部署との摩擦を招きます。特に、現行システムの棚卸しや移行範囲の明確化ができていない場合、後工程で「対象外のサーバが後から発覚」「データ依存関係が未確認」などの問題が頻発します。
課題例
現行システムの棚卸しが不十分で、移行対象外のサーバやアプリが後から発覚
移行範囲が曖昧で優先順位付けがされていないため、計画が二転三転
移行ツールや手順の事前検証不足で、本番移行時にトラブル発生
防止策
初期段階でアプリケーション依存関係の可視化を徹底する
PoC(概念実証)を行い、手順・ツールの適用可否を確認
移行対象とスコープをドキュメント化し、関係者全員で合意してから開始
AWSにシステムを移行しても、移行後の運用設計が不十分だと手戻りが発生します。IAM権限設計や監視体制、バックアップ方針などが曖昧なまま運用を開始すると、セキュリティ事故や障害対応遅延のリスクが高まります。移行作業と並行して運用設計を固めておくことで、移行後の安定稼働を実現できます。
課題例
移行後のAWS運用体制が整っておらず、設定変更が場当たり的
権限設計(IAM)が曖昧で、セキュリティリスクが増大
運用監視の統合が不十分で、障害検知が遅れる
防止策
移行計画と並行して運用設計を事前に策定する
IAMルール、監視体制、バックアップポリシーを明確化
AWS運用チームを立ち上げ、スキルトレーニングを早期に開始
AWS移行では、オンプレミスとAWS間の接続、AWS内部のVPC構成など、複雑なネットワーク設計が求められます。CIDRやルーティング設計が不適切だと、移行後にシステム間通信が遮断されたり、転送速度が大幅に低下するなどのトラブルが発生します。オンプレとクラウドの両視点で綿密にレビューすることが欠かせません。
課題例
VPC設計やCIDR計画が不十分で、サブネットが衝突
オンプレとAWS間の接続方式が適切でなく、転送速度や安定性に問題
ファイアウォール設定やセキュリティグループの穴あき設定で通信不可
防止策
ネットワーク設計をオンプレとAWS双方のチームでレビュー
初期はVPN接続、本番移行時はDirect Connectに切り替える構成を検討
CIDRやルートテーブルをドキュメント化し、変更管理を徹底
移行作業がスムーズに完了しても、データ整合性が担保されていないとシステム障害や業務停止につながります。特に大規模データベースやファイルサーバ移行では、同期ミスや欠損が発生しやすいため、移行後のチェック体制を事前に整えることが重要です。
課題例
データ移行後、整合性チェックを行わずに本番稼働
大規模DB移行時に差分データが同期されず、システム障害発生
ファイル転送中の暗号化やエラー検知が不十分
防止策
移行テストフェーズを必ず設ける
AWS Database Migration Service(DMS)やDataSyncを活用し、転送ログを監視
チェックサムやレコード件数比較でデータ整合性を確認
クラウドは柔軟な課金モデルが魅力ですが、移行後に構成を見直さないまま運用すると、オンプレ時代よりコストが増大することもあります。リザーブドインスタンスの未活用や、転送料金・バックアップストレージなどの隠れコストが見積もりから漏れやすい点に注意が必要です。移行初期からコストモニタリングを行い、早期に最適化を図ることが成功の鍵です。
課題例
移行後もオンプレと同じ構成を維持してしまい、クラウド特性を活かせない
リザーブドインスタンスやSavings Plansを未活用でオンデマンド課金が膨張
移行ツール利用やデータ転送料金を事前見積もりに含め忘れた
防止策
移行直後にAWS Cost ExplorerやTrusted Advisorでコストを可視化
早期にリソース利用パターンを分析し、予約型課金を適用
データ転送やストレージ費用も含めたTCO分析を事前に実施
