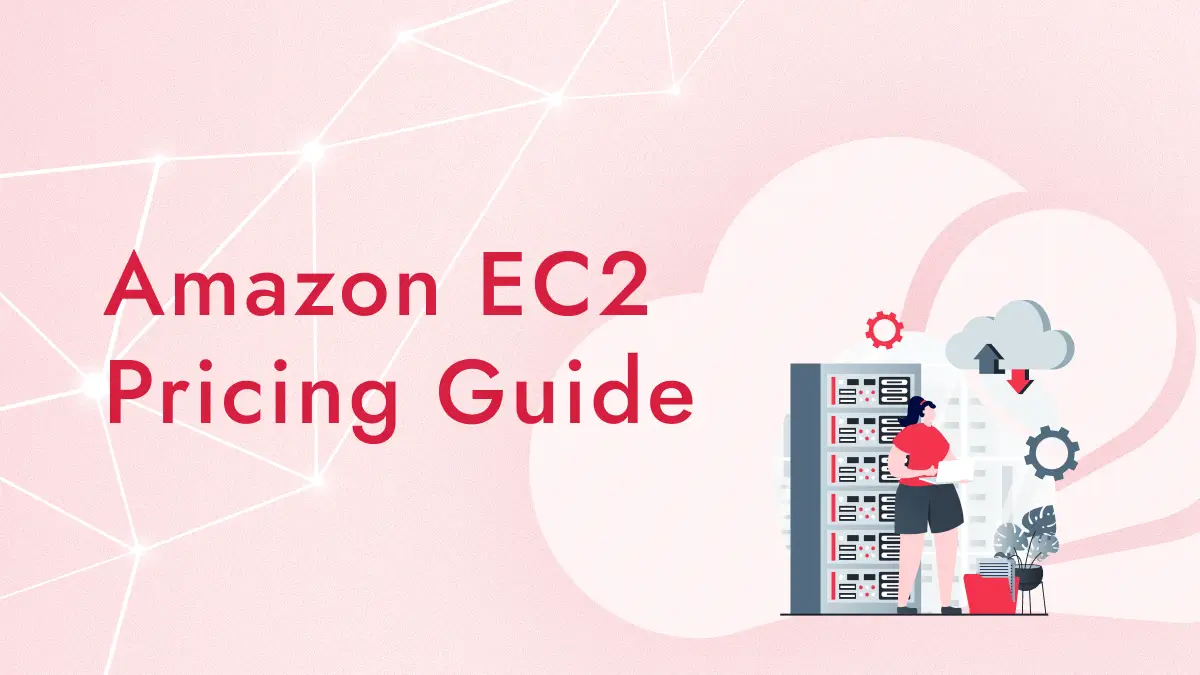
- Amazon EC2
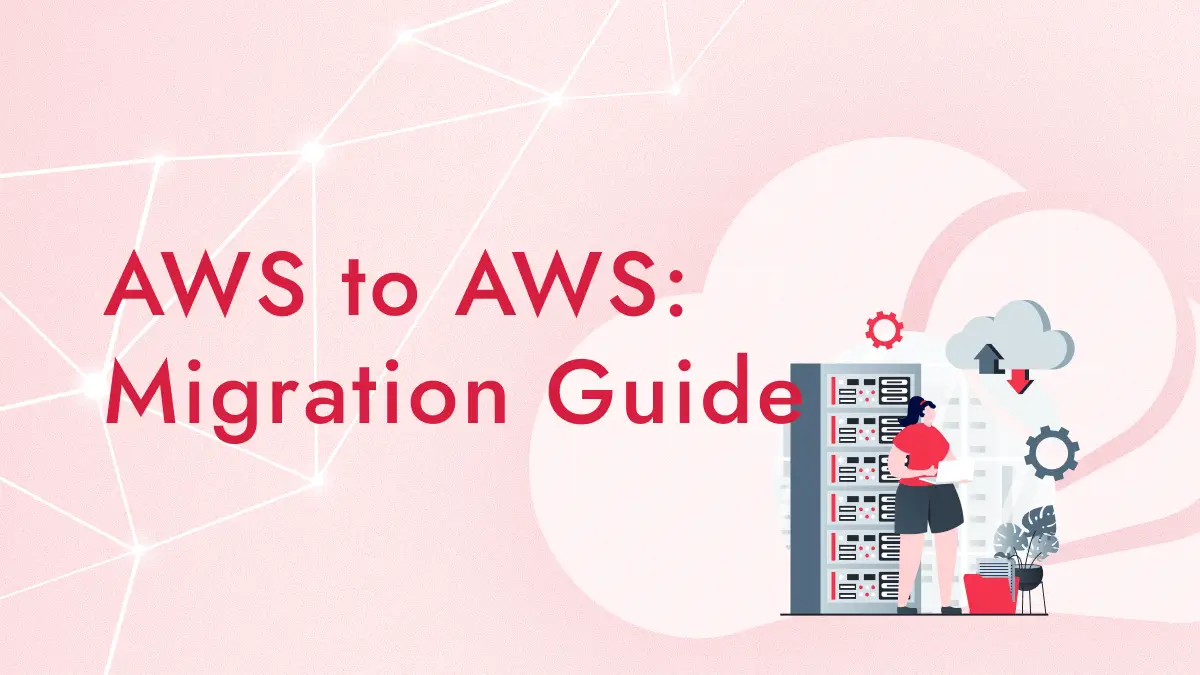
AWSアカウント間でリソースを移行する場面は、組織改編やセキュリティ強化、環境分離などさまざまです。S3、EC2、RDSなど、サービスごとに移行方法や制約が異なるため、適切な手順を理解しておかないと、データ損失や運用トラブルにつながる恐れがあります。
本記事では、AWS同士の移行を安全かつ効率的に進めるために、主要サービス別の移行方法やツール、構成パターンを解説。初めての別アカウント移行でも迷わず計画できるよう、実務に役立つポイントをまとめます。
AWSアカウント間でリソースを移行する必要が生じる背景には、組織や事業の変化、セキュリティ要件の見直しなどがあります。実務でよく発生する4つの代表的なケースを解説します。
グループ企業間でAWSアカウントを複数運用している場合、組織改編や子会社統合に伴ってアカウントを集約することがあります。複数アカウントが乱立している状態では、コスト管理やセキュリティ統制が複雑化し、運用負荷も増大します。
典型的なシナリオ
親会社が子会社のシステムを取り込み、統一ポリシーで管理したい
統合後にAWS Organizationsでアカウントを一元管理したい
複数アカウントの請求を統合し、コストを最適化したい
こうしたケースでは、既存リソースを安全に移行しながら、統合後の運用設計を同時に進める必要があります。
セキュリティ要件や社内ルールの変更により、既存アカウントでは管理しきれない状況が発生することがあります。
移行の背景例
過去に暫定で構築したAWS環境を、セキュリティ基準に適合させたい
誰でも管理者権限を持っている状態を解消したい
権限分離を徹底するため、重要システムを新しいアカウントに分離したい
IAMポリシーやクロスアカウントアクセスを慎重に設計した上でリソース移行を行い、運用をクリーンな状態に刷新します。
開発・検証と本番が同一アカウント内で運用されている場合、以下のリスクがあります。
開発チームが本番リソースに誤って操作してしまう
テストデータと本番データが混在し、監査上の問題が発生
リソースが複雑化してコスト管理が困難になる
こうしたリスクを回避するため、開発・検証環境を別アカウントに移行し、本番環境と物理的に分離する手法が一般的です。こうすることで権限管理をシンプルにし、障害やヒューマンエラーを未然に防げます。
レアケースですが、事業売却やアウトソーシング先の変更など、事業構造の変化による要因もあります。
例1:事業売却
売却対象の事業に関連するAWSリソースを、買い手側が管理するアカウントに移行する。
例2:委託先変更
システム運用を委託していた外部ベンダーから、別の委託先や自社運用に切り替える際にAWS環境を移す。
データ保全とセキュリティ維持が特に重要です。移行作業の透明性を確保するため、作業ログや権限管理を厳密に記録しながら進める必要があります。
ここでは、計画段階で確認するべきポイントを解説します。
AWS間移行は、ファイルやデータを単純にコピーする作業とは異なります。各AWSサービスには独自の移行手順や制約があり、それらを無視して進めるとデータ損失やサービス停止につながるリスクがあります。
サービスごとに手順・制約が異なる
例:S3はクロスアカウントコピーで移行可能ですが、RDSはスナップショット共有が必要です
EC2はAMIコピーが使えますが、Elastic IPやセキュリティグループは再設定が必要です
依存関係を把握する重要性
EC2、RDS、ECSなどが複雑に連携している場合、移行順序を誤るとサービスが正常に動作しません
事前にシステム構成図や依存関係リストを作成し、移行計画に反映させることが不可欠です
AWSアカウント間移行では、移行元と移行先のアカウント間で適切な権限を設計する必要があります。
権限設計の基本
IAMロールを使い、クロスアカウントアクセスを安全に実装する
最小権限の原則に基づき、必要な操作だけを許可
移行用の一時的な権限と、運用後の恒常的な権限を分けて管理
クロスアカウントアクセスの設定
S3やDMSなど一部のAWSサービスは、クロスアカウント機能を利用することで安全にリソース共有できます
リソースポリシーや信頼ポリシーを適切に設定し、アクセス経路を明確化することが重要です
ポイント
IAMの設定ミスは移行作業全体を止める原因となるため、PoC(Proof of Concept:概念実証)でテストしておくことをお勧めします
AWS間で大量データを転送する場合、ネットワークの構成とセキュリティ対策を慎重に設計する必要があります。
VPC PeeringやTransit Gatewayの活用
少数のVPC間接続ならVPC Peeringがシンプルで低コスト
複数アカウント・複数VPCを統合する場合はTransit Gatewayが適している
データ転送時のセキュリティ対策
データはTLSによる暗号化通信を必須とする
S3間コピーではSSE-KMSによる暗号化を併用する
Direct Connectを利用する場合は、VPN併用による二重保護を検討
注意点
ネットワーク帯域が不足すると移行に大幅な時間がかかります。事前に転送量を試算し、必要に応じて帯域を増強しましょう
AWSアカウント間の移行は、段階を踏んで計画的に進めます。ここでは、初期準備から運用切り替えまでの流れをステップごとに解説します。
移行プロジェクトは、現状把握からスタートします。移行対象となるAWSリソースをすべて洗い出し、依存関係を整理しましょう。
棚卸しで確認すべき項目
EC2、RDS、S3など主要リソースの一覧
各リソースが利用するネットワーク、IAM、セキュリティグループ
システム間の接続関係、外部連携の有無
利用中のリージョンとサービス制約
これらを踏まえて、優先度・リスク・移行順序を決定し、全体スケジュールと担当範囲を明確化します。
いきなり本番移行を実施するのはリスクが高いため、PoCを行います。
小規模なサンプルリソースを移行し、手順の妥当性を検証
データ転送速度、ダウンタイム、コストを事前に把握
IAMやネットワーク設定に不備がないかを確認
PoCで得た知見をもとに、移行計画を改善することで、後工程でのトラブルを未然に防ぎます。
本番移行では、業務影響を最小化するスケジュール設計が重要です。
ポイント
ダウンタイムをどこまで許容できるかを事前に合意
移行作業を業務時間外や休日に実施する計画を立案
Blue/Greenデプロイや段階的切り替えでリスクを低減
事前にロールバック手順を定義しておく
こうすることで、万が一の障害時にも迅速に復旧できます。
本番移行では、事前計画に沿って慎重に作業を進めます。サービスごとに異なる手順を遵守し、各ステップでテストを実施します。
移行中のチェック項目
データ転送が正常に完了しているか
IAMやセキュリティ設定が適切か
移行後のリソースが期待通りに稼働しているか
検証不足のまま本番切り替えを行うと、移行後に重大な障害が発生するリスクが高まります。
移行作業が完了したら、新しいAWSアカウントでの運用体制に切り替えます。
CloudWatchやAWS Configで監視基盤を再構築
IAMポリシーやログ設定を再確認
移行元アカウントで不要になったリソースを安全に削除
運用マニュアルを更新し、関係者に共有
このフェーズを疎かにすると、移行後のセキュリティホールや運用トラブルにつながります。移行完了後も数週間は監視を強化し、安定稼働を確認しましょう。
AWSアカウント間移行では、サービスごとに最適な移行方法やツールが異なるため、個別に戦略を立てる必要があります。よく使われる主要サービスの移行手法を解説します。
Amazon S3はクロスアカウントコピー機能が提供されており、比較的スムーズに移行できます。ただし、データ容量やバケットポリシーによって手順が異なるため、事前に設計が必要です。
クロスアカウントコピー
S3クロスアカウントアクセスを設定し、バケット間で直接コピー可能
バケットポリシーに移行先アカウントを明示的に許可する必要がある
S3 Batch Operations
数百万オブジェクト以上を効率的にコピーする場合に有効
マニフェストファイルを作成し、一括移行を自動化できる
AWS CLI活用例
小規模データはCLIでコピー可能。
例:aws s3 sync s3://source-bucket s3://target-bucket --source-region ap-northeast-1 --region ap-northeast-1
ポイント
転送中はSSE-KMS暗号化を利用し、セキュリティを確保することが推奨されます
Amazon EC2インスタンスはAMIを活用して移行するのが基本です。ただしElastic IPやセキュリティグループなどは再設定が必要になります。
AMI共有/コピー
AMIを移行先アカウントに共有し、そのAMIから新しいEC2を起動
コピー時に暗号化キー(KMS)設定を移行先アカウントでも使用可能にする
AWS MGNの活用
稼働中のEC2をリアルタイムレプリケーションで移行できる
ダウンタイムを最小化したい場合に適している
Elastic IPの取り扱い
Elastic IPはアカウント間で移行できないため、新規に割り当てが必要
DNS設定変更を計画に含めることが重要
Amazon RDSはスナップショットやデータベース移行ツールを使って移行します。業務影響を抑えるには、移行方法の選定が鍵になります。
スナップショット共有
スナップショットを移行先アカウントに共有し、リストアして新しいRDSを構築
シンプルで確実だが、ダウンタイムが発生する
AWS Database Migration Service(DMS)
稼働中のDBをほぼリアルタイムでレプリケーション可能
ダウンタイムを極力短縮したい場合に有効
コンテナ環境は、ECR(Elastic Container Registry)の移行が中心です。
Amazon ECRイメージ移行
docker pullで移行元ECRから取得し、docker pushで移行先に登録
AWS CLIスクリプトやCodePipelineを使って自動化も可能
Amazon ECS/Amazon EKS設定
ECSタスク定義やEKSマニフェストはJSON/YAML形式でエクスポートし、移行先アカウントで適用する
IAMや各種設定情報は、自動コピーができないため再構築が必要です。ここがAWSアカウント間移行の最も手間がかかる部分のひとつです。
手動再構築
IAMユーザー、ロール、ポリシーを新規作成
移行元アカウントの構成を参考に一から設定する
IaC(Infrastructure as Code)活用
CloudFormationやTerraformを使ってコード化し、移行先で再構築
再現性が高く、複雑な設定でもミスを防ぎやすい
ポイント
IAMは最小権限設計を徹底し、移行後に不要な権限が残らないよう注意しましょう
AWSアカウント間の移行では、移行期間中の運用継続性やセキュリティ要件に応じて、どの構成で移行を進めるかを決定する必要があります。代表的な3つのパターンを紹介し、それぞれの特徴と設計のポイントを解説します。
もっとも一般的な方法が、クロスアカウントアクセスを利用した段階的移行です。移行元と移行先アカウント間で一時的にリソースを共有し、順次移行を進めていきます。
特徴
両アカウントを並行稼働させながら少しずつ移行できる
検証環境を先に移行し、本番環境は最終段階で切り替え可能
ダウンタイムを最小限に抑えられる
設計のポイント
S3やRDSはクロスアカウント機能を利用して安全にデータ共有
IAMロールを使い、最小権限でアカウント間アクセスを設計
移行期間中はコストが二重発生するため、スケジュールを明確化する
適しているケース
検証しながら段階的に移行したい場合、または本番停止時間を極力短くしたい場合
一時的に共有VPC(Shared VPC)を構築し、移行元・移行先アカウント双方が同じVPC上でリソースを利用する構成です。
特徴
ネットワーク接続やセキュリティグループの設定を最小限で済ませられる
データ転送を同一VPC内で行えるため、速度と安定性が向上
移行完了後に共有VPCを削除することで、後処理が簡単
設計のポイント
Shared VPCを管理する専用アカウントを用意
サブネットやルートテーブルの設計を事前に定義
移行終了後は不要な権限を速やかに削除してセキュリティを確保
適しているケース
大量データ移行や複雑なネットワーク接続を伴うシステムに適している
旧アカウントから新アカウントへの一括切り替え型移行です。移行期間を短く設定し、一度にすべてのリソースを移行します。
特徴
移行期間が短く、二重運用によるコストが発生しにくい
設計がシンプルで管理が容易
一方で、トラブルが発生した場合の影響範囲が大きい
設計のポイント
事前にPoCで手順を検証し、ダウンタイムを正確に見積もる
ロールバック計画を用意しておく
本番リリース前にステージング環境で最終リハーサルを実施
適しているケース
小規模な環境や、停止時間を数時間確保できる場合
移行構成の選定は、システム規模・移行期間・許容ダウンタイムによって最適解が異なります。初期段階でクロスアカウントアクセスを利用した段階移行を行い、最終的に完全切り替えを行う「ハイブリッド型」のアプローチを採用するケースもあります。
ここでは、実務で多い失敗例と回避策を解説します。
移行元・移行先アカウント間でIAMロールやポリシーを適切に設定できていないと、移行作業が中断されることがあります。S3やRDSのクロスアカウント共有機能を利用する場合は、バケットポリシーやKMSキー権限まで考慮する必要があります。
失敗例
AMI共有時にKMSキーの権限を付与しておらず起動できない
DMSでデータレプリケーションが開始できない
S3コピー時にAccess Deniedエラーが発生
回避策
PoC段階で権限設定を事前にテスト
最小権限をベースにしつつ、必要に応じて一時的に権限を拡大
AWS公式の「IAMポリシーシミュレーター」で動作確認を実施
AWSの一部サービスはリージョンごとに提供状況や機能に差があります。移行先リージョンで同じサービスが利用できないケースがあり、事前確認が必須です。
失敗例
RDSスナップショットを共有できないリージョンを選択
ECSやEKSで一部インスタンスタイプが未提供
Aurora Global Databaseなどリージョン制限のある機能を使用していた
回避策
事前にAWSリージョン別サービス一覧を確認
使用中の機能が移行先リージョンで提供されているかチェック
制約がある場合は代替構成をPoCで検証しておく
AWS間で大量データを転送する場合、時間とコストの想定が甘いと移行計画が破綻します。
失敗例
数十TBのS3データを転送する計画が帯域不足で大幅遅延
Direct Connectを使わずVPN接続で移行し、数週間かかる
転送料金を見積もりに含め忘れ、予算超過
回避策
データ容量と帯域を計算して所要時間を試算
大容量の場合はAWS Snowballなど物理転送サービスを活用
転送料金を事前に計算し、コスト監視を強化
移行そのものが完了しても、移行後の設定不備が原因で障害やセキュリティリスクが発生するケースがあります。
失敗例
IAMポリシーが不十分で本番運用が開始できない
CloudWatchアラームや監視設定を再構築しておらず障害検知が遅れる
S3バケットが公開状態のまま稼働
回避策
移行後に「構成チェックリスト」で設定を確認
AWS ConfigやSecurity Hubでセキュリティ監査を自動化
移行完了後も一定期間は監視を強化して早期に問題を発見
いずれも事前準備と検証不足が原因で発生します。PoCやチェックリストを活用して計画段階からリスクを洗い出すことで、多くの問題を未然に防ぎ、安全でスムーズなAWS間移行を実現できます。
AWSアカウント間の移行は、単なるコピー作業ではなく、計画と検証が不可欠なプロジェクトです。サービスごとの制約を把握し、PoCで手順を確認することで、移行中のトラブルを大幅に減らせます。また、段階的な移行やクロスアカウントアクセスを活用しつつ、移行後は監視・セキュリティ設定を見直して、安定したクラウド運用を実現しましょう。
AWS の使い方、見積もり、構成、運用などで迷いや不安がある場合は、お気軽にご相談ください。現地チームとの共通認識づくりや前提条件の整理から、判断をスムーズに進めるお手伝いをします。
本サービスは、日本で最初の商用インターネットサービスプロバイダーとして誕生した IIJ グループと、AWS プレミアティアサービスパートナーであるサーバーワークスが共同で提供する「IIJ Managed Cloud for AWS」です。東南アジアを含むグローバル環境での利用にも対応し、現場の判断に寄り添った AWS 支援を行っています。
▶ 詳しい資料を確認する
▶ AWS活用の相談をしてみる
