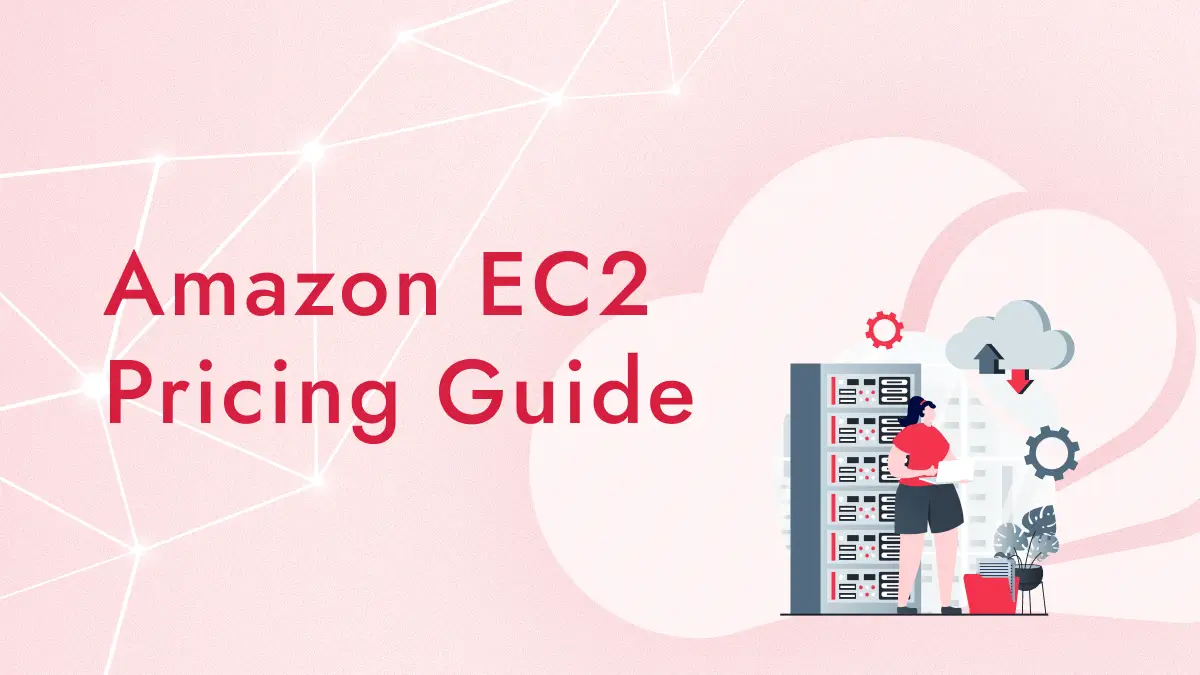
- Amazon EC2
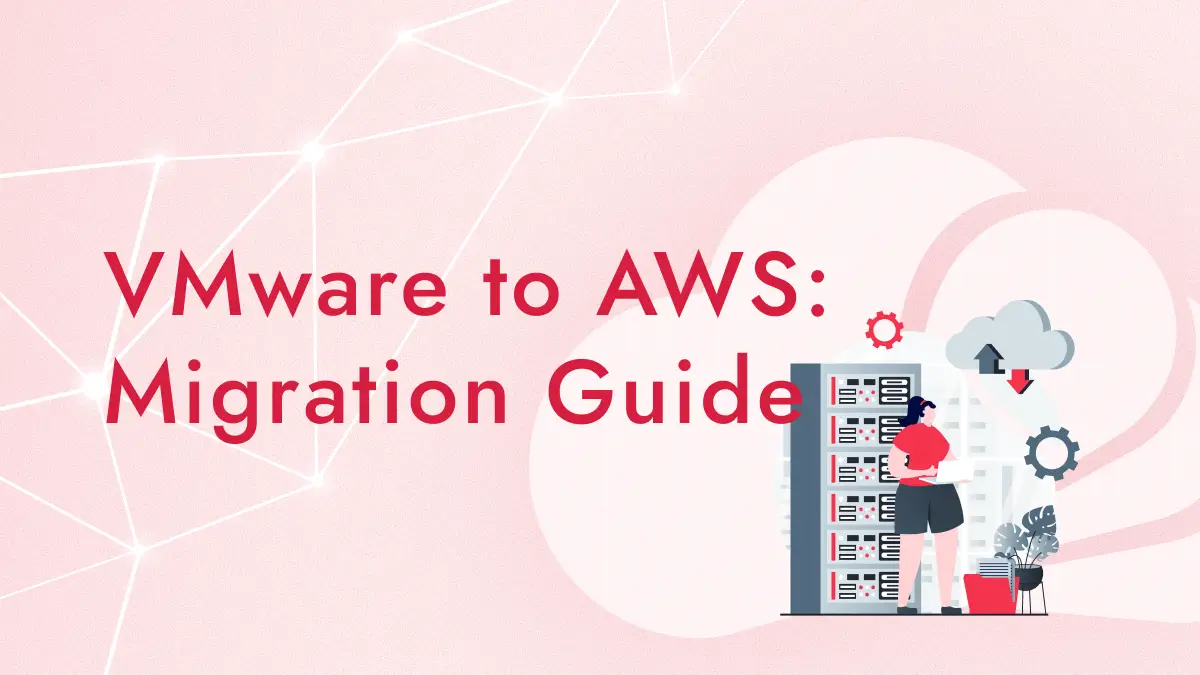
オンプレミス環境で稼働しているVMware仮想マシンをAWSへ移行する企業は増えています。ハードウェアの老朽化や運用コストの高騰、BCP対策や拡張性の確保など、クラウド移行には多くのメリットがあります。しかし実際の移行では、「どのツールを使うべきか」「どの手順で進めれば安全か」「ダウンタイムをどこまで短縮できるか」といった課題が立ちはだかります。
本記事では、VMware環境からAWSへの移行に特化し、代表的な移行ツールであるAWS MGNやVM Import/Exportの特徴と使い分け、移行手順の全体像、構成パターン、そして現場で注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
オンプレミス環境でのシステム運用は、長年企業のIT基盤を支えてきました。しかし、近年はその維持・運用に多くの課題が生じています。
まず大きな問題はハードウェアの老朽化と保守コストの増大です。サーバやストレージは数年単位で更新が必要ですが、更新サイクルが短縮され、部品代や保守契約費用も年々上昇しています。更新作業にはシステム停止が伴うため、業務への影響を避けるための計画や人員確保にもコストがかかります。
次に、災害対策やBCP(事業継続計画)の限界です。オンプレミス環境でシステムを二重化し、遠隔地へのバックアップや冗長構成を構築するには、多額の初期投資と継続的な維持管理コストが必要です。実際には、BCP対策の重要性を認識しながらも、十分な対策を取れない企業も少なくありません。
スケーラビリティ不足と運用負荷も深刻です。アクセス数やデータ量が急増しても、オンプレミスではハードウェア増設が間に合わず、ピーク需要に対応するために過剰なリソースを常時確保せざるを得ません。結果、余剰分が無駄な固定費として積み上がり、IT部門には障害対応やパッチ適用などの運用負担が重くのしかかります。
これらの課題を解決する手段として、注目されているのがAWS(Amazon Web Services)への移行です。AWSを活用することで、従来のオンプレミス環境では実現が難しかった柔軟性と効率性を得ることができます。
まず「初期投資削減とコスト最適化」です。
オンプレミスで必要だったサーバやネットワーク機器の購入が不要になり、初期投資を大幅に削減できます。AWSは従量課金モデルで、使用した分だけ支払う仕組みのため、リソースを柔軟に増減でき、無駄な固定費を減らせます。リザーブドインスタンスやSavings Plansといった料金オプションを活用すれば、継続利用時のコストも効率的に抑えられます。
次に「高可用性と耐障害性の向上」です。
AWSは複数のデータセンター(AZ:アベイラビリティゾーン)を活用した冗長構成を容易に構築でき、システム障害が発生しても自動的に切り替えが行われるため、災害時でも業務を継続できる基盤が整います。
さらに「最新サービス活用による運用効率化」も大きな魅力です。
RDSやECS、Lambdaといったマネージドサービスを活用することで、サーバ保守やパッチ適用といった作業を削減できます。監視や自動化もCloudWatchやEventBridgeといったAWSサービスで統合でき、少人数でも効率的な運用体制を実現できます。
こうしたメリットにより、企業はシステム維持コストを削減しつつ、事業拡大や新規サービス開発により多くのリソースを投下できるようになります。これが、オンプレミスからAWSへの移行が加速している最大の理由です。
VMwareからAWSへの移行は、単なるシステム引っ越しではなく、ビジネスに大きな影響を与えるプロジェクトです。準備不足のまま進めると、ダウンタイムが長引いたり、運用コストが予想以上に膨らむといった問題が発生しかねません。ここでは、移行をスムーズかつ安全に進めるための準備を解説します。
まずは、現在稼働しているオンプレミス環境の正確な把握と可視化です。
vCenterやvSphereなどの管理ツールを使い、仮想マシンの台数、CPU・メモリ・ストレージ容量などのハードウェアリソースを詳細に洗い出します。加えて、アプリケーションやミドルウェアの依存関係も整理しておきましょう。
特に、どのアプリケーションがどのVM上で稼働しているか、外部システムとの連携はどうなっているかを把握することが重要です。依存関係を見落とすと、移行後に「一部のシステムが動かない」「連携が途切れた」といったトラブルが発生しかねません。
棚卸し結果は図や表で可視化し、関係者全員が同じ情報を共有できる状態にしておくと、移行計画の策定がスムーズになります。
「なぜAWSへ移行するのか」「移行後に何を達成したいのか」を明確にしておく必要があります。たとえば以下の要件をあらかじめ定義しておきましょう。
可用性目標:システム停止時間をどの程度まで許容するのか
セキュリティ要件:アクセス管理、暗号化、監査ログの整備レベル
運用コスト目標:クラウド利用料をどの程度に抑えたいか
ダウンタイム許容範囲:本番切り替え時に業務をどこまで止められるか
移行スケジュール:段階移行なのか、一括切替なのか
これらを定義しておくことで、適切な移行方式やAWSサービスを選定できるだけでなく、移行後の運用設計にもブレがなくなります。
AWS移行では、オンプレミスとクラウド間を安全かつ安定的に接続することが前提となります。代表的な接続方式にはVPN接続とAWS Direct Connectがあります。
VPN接続
短期間で構築でき、初期コストを抑えられる
ただし帯域は限られ、大規模移行では速度不足になる可能性あり
Direct Connect
専用線による高帯域・低遅延接続
本番稼働や大容量データ移行に適している
移行初期はVPNで開始し、本番切替のタイミングでDirect Connectへ切り替えるハイブリッド構成を採用する企業も多く見られます。
また、AWS側のVPC設計やセキュリティグループのルール設定も事前に準備が必要です。IPレンジやポート要件を整理しておかないと、移行後に通信が遮断されるリスクがあります。ネットワーク設計は、オンプレとAWS双方の担当者でレビューを行い、認識齟齬がない状態で移行作業に進みましょう。
典型的な移行フローを6ステップに分けて解説します。
最初に、実際の移行を小規模に試すPoC(Proof of Concept:概念実証)を実施します。
本番システムをいきなり移行すると、想定外のトラブルで業務が停止するリスクがあります。PoCでは、テスト用のVMや限定的なシステムを対象に、以下を確認します。
移行ツールの動作確認(AWS MGNやVM Import/Export)
ネットワーク接続の安定性と転送速度
ダウンタイムの見込み時間
AWS上でのシステム動作(互換性やパフォーマンス)
問題点を洗い出し、対策を検討することで、本番移行のリスクを最小化できます。
PoCの結果を踏まえ、移行方式と使用するツールを正式に決定します。
VMwareからAWSへの移行では、主に以下の2種類の方式があります。
リフト&シフト(Re-host)
既存VMをほぼそのままAWSへ移行。短期間で移行可能だが、最適化は限定的
→ AWS MGNが最適
再構成(Re-platform/部分モダナイズ)
一部をAWSマネージドサービスへ置き換える方式。移行コストは増えるが、運用負荷を削減できる
→ AWS MGN+RDSやEFSなどのサービスを併用
移行の規模、ダウンタイム許容範囲、コスト制約を基準に、最適な方式を選択しましょう。
移行先となるAWS環境を構築し、オンプレミスとの接続を準備します。
VPC設計
移行後の運用を見据え、サブネットやセキュリティグループを設定
接続方式の選定
VPNかDirect Connectを選び、接続を構築
IAM設計
権限管理を明確に定義
監視設定
CloudWatchなどで監視基盤を構築
IPレンジや通信ポートなどを事前に整理しておかないと、移行後に通信トラブルが発生する恐れがあります。
準備が整ったら、移行対象VMをAWSにコピーします。大規模環境ではAWS MGNを使い、オンプレミスのVMをAWS上にリアルタイムでレプリケーションします。移行直前までオンプレとクラウドの状態を同期でき、ダウンタイムを最小限に抑えられます。
小規模な移行や検証環境であれば、VM Import/Exportを利用して、VMイメージをAWSに直接インポートすることも可能です。
レプリケーション後は、AWS上でテスト移行を実施します。
以下の観点で検証を行い、問題があれば本番移行前に解消しておきます。
システムがAWS上で正常に稼働するか
アプリケーション間の依存関係に問題はないか
ネットワークや外部接続が正しく動作するか
パフォーマンスが要件を満たしているか
テスト結果はドキュメント化し、関係者全員で合意してから本番移行に進みます。
最後に、本番システムをAWS上に切り替えます。影響を最小化するため、Blue/Greenデプロイやカナリアリリースを活用して段階的に切替を行うのがおすすめです。
切替後は、AWS上で稼働中のシステムを監視し、問題がなければオンプレミス環境を順次停止します。また、移行直後はAWS Cost Explorerなどを活用し、リソース利用状況を分析して無駄なコストを最適化していきましょう。
AWS純正ツールを中心に、旧サービスやサードパーティ製ツールの位置付けを整理して解説します。
AWS MGNは、現在AWSが推奨している標準的な移行ツールです。オンプレミスのVMをAWS上にリアルタイムでレプリケーションでき、切り替え時のダウンタイムを最小限に抑えられる点が最大の強みです。
特徴
継続的なデータ同期により、移行直前までオンプレ環境とクラウド環境を同一状態で保てる
ダウンタイムを短くでき、ミッションクリティカルなシステムでも安心
AWS公式サービスのため、サポート体制が充実
適用シーン
本番稼働中の業務システムなど、業務影響を最小化したいケース
数十台以上のVMをまとめて移行する大規模プロジェクト
VM Import/Exportは、VMwareの仮想マシンイメージをそのままAWSにインポート/エクスポートできるサービスです。AWS MGNのような継続レプリケーション機能はありませんが、簡単にVMをAWS上に持ち込めます。
特徴
VMイメージを直接AWSにアップロードし、AMIとして利用可能
逆にAWSからVMware環境へエクスポートも可能
構成変更が不要で、小規模移行に適している
適用シーン
小規模な検証環境や開発環境の移行
ダウンタイムをある程度許容できるシステム
AWS⇔オンプレ間でVMを行き来させたいケース
かつてはCloudEndure MigrationがAWS公式ツールとして提供されていましたが、現在はAWS MGNに統合されており、新規導入は推奨されていません。既存環境で利用していた場合も、今後はAWS MGNへの移行が基本方針となります。
AWS MGNはCloudEndureの技術を継承しており、UIや機能面が改善されているため、これから移行を計画する企業はAWS MGNを選択すべきです。
AWS公式ツールで対応できない特殊要件がある場合は、サードパーティ製ツールを検討することもあります。以下のポイントを比較しましょう。
対応仮想化基盤:VMware以外(Hyper-V、KVMなど)への対応状況
自動化機能:移行計画、テスト、切り替え手順をどこまで自動化できるか
コスト構造:ライセンス料、従量課金、サポート費用を含めたトータルコスト
サポート体制:日本語対応、24時間サポート、AWSとの連携体制
セキュリティ・コンプライアンス対応:暗号化、ログ管理、規制対応状況
ただし、AWSが公式で提供しているAWS MGNとVM Import/Exportでほとんどの移行ニーズはカバー可能です。サードパーティを検討するのは、複雑なマルチクラウド環境や特別なコンプライアンス要件がある場合に限定されます。
VMwareからAWSへ移行した後の構成は、移行目的や成長戦略によって大きく変わります。ここでは、代表的な3つのパターンを紹介します。
最もシンプルな構成は、既存のVMware環境をそのままAWS上に再現する「リフト&シフト」型です。
特徴
既存システムの構成をほぼ変更せず、AWSのEC2上で稼働させる
設計工数が少なく、短期間で移行できるのが最大のメリット
メリット
早急にオンプレ機器の保守切れや障害リスクを回避できる
設定変更やアプリケーション改修が最小限で済むため、初期コストが低い
注意点
AWSの特性を活かしきれず、コスト最適化は限定的
運用負荷やセキュリティ課題がオンプレ時代と変わらない場合がある
スピード重視でとりあえずクラウド上に移行し、その後段階的に改善していく戦略を取る場合に適しています。
移行後にAWSのマネージドサービスを活用し、少しずつ運用を最適化していく構成です。
特徴
Lift & Shiftで移行したシステムの一部を、AWSのマネージドサービスに置き換える
DBをAmazon RDSに移行、ログをCloudWatch Logsに統合、Auto Scalingで可用性を向上するなどが一般的
メリット
運用負荷を軽減し、障害対応や保守作業を削減
徐々にクラウドネイティブ化するため、リスクを分散できる
コスト効率を中長期的に最適化できる
活用例
Auto Scalingで負荷に応じてEC2を自動増減
AWS Backupでバックアップポリシーを一元管理
CloudWatchやEventBridgeで監視・通知を自動化
初期移行時に大きな変更を避けつつ、時間をかけて最適化を進めたい企業に適した構成です。
システムをクラウド前提でゼロから設計し直す、本格的なクラウドネイティブ化のアプローチです。
特徴
従来のモノリシック構成を分割し、マイクロサービスやサーバレスアーキテクチャを採用する
代表例としては、EKSによるKubernetes運用や、AWS Lambdaを活用した完全サーバレス構成などがある
メリット
開発スピードの向上とスケーラビリティ確保
運用の自動化が進み、少人数で大規模システムを管理可能
ビジネス要件の変化に即応できる柔軟な基盤を構築できる
注意点
設計・開発工数が大きく、短期移行には不向き
高度なAWSスキルや体制が必要
長期的に事業を成長させたい企業や、システムの技術的負債を解消したい場合に最適な構成です。
計画不足や設計ミスによって移行後にトラブルが発生するケースも少なくありません。ここでは、実務でよく見られる失敗とその対策を紹介します。
オンプレミスで利用していたソフトウェアライセンスが、AWS移行後もそのまま利用できるとは限りません。特にWindows ServerやSQL Serverなどは、クラウド環境で利用する際のライセンス形態が異なる場合があります。
よくある失敗例
BYOL(Bring Your Own License)の要件を満たさず、監査時に指摘される
ライセンス条項を確認せずに移行した結果、追加コストが発生
古いOSバージョンがAWSでサポートされていない
対策
移行計画段階でソフトウェアベンダーとライセンス条件を確認する
AWS専用ライセンス(License Included)を活用する
必要に応じてOSを最新バージョンにアップグレードしてから移行する
AWSはセキュリティ機能が豊富ですが、設定を誤ると重大なリスクにつながります。移行後に設定不備が発覚するケースもあります。
よくある失敗例
セキュリティグループを「0.0.0.0/0」で開放したまま運用
IAMポリシーが曖昧で権限が過剰付与されている
ログ監視や暗号化設定を未実施で運用開始してしまう
対策
IAMは最小権限の原則で設計し、運用ルールを明文化
AWS ConfigやSecurity Hubを活用し、設定を自動チェック
CloudTrailやCloudWatch Logsで監査ログを取得・監視する
初期段階からセキュリティ担当者をプロジェクトに参画させる
AWSへの移行では、大量のVMやデータをクラウドへ転送するため、ネットワーク帯域がボトルネックになりがちです。
よくある失敗例
VPN接続のみで移行を開始した結果、転送速度が遅すぎてスケジュールが遅延
Direct Connectを利用していたが、帯域設計が不十分で移行中に通信が輻輳
ネットワーク機器の設定不足で通信断が発生
対策
初期PoC段階で実際の転送速度を計測し、必要帯域を見積もる
大規模移行ではAWS Direct Connectを活用する
数百TB以上のデータ移行にはAWS Snowballを併用して帯域負荷を軽減
ネットワーク設計はオンプレとAWS双方のチームでレビュー
移行作業自体は完了しても、運用体制が整っていないまま本番稼働を開始すると、トラブル発生時に対応が遅れます。
よくある失敗例
AWS上で障害が発生してもアラートが飛ばない
バックアップは取得していたが、リストア手順が未検証で復旧できない
運用担当者のAWSスキル不足により設定変更ミスが発生
対策
CloudWatchやEventBridgeを活用してアラートを整備
定期的な復旧テストを実施し、RTO/RPOを確認
運用チームに対してAWSトレーニングを実施
運用設計書を作成し、関係者間で共有
VMwareからAWSへの移行は、準備・ツール選定・段階的な移行計画が成功の鍵です。まずは現状把握とPoCでリスクを洗い出し、AWS MGNなどを活用して安全に移行します。
移行後は、最初は「Lift & Shift」でスピード重視、その後にモダナイズやリファクタリングで最適化していくのが現実的です。ライセンス、セキュリティ、ネットワーク、運用設計といった典型的な失敗要因を事前に対策し、長期的に活用できるクラウド基盤を構築しましょう。
AWS の使い方、見積もり、構成、運用などで迷いや不安がある場合は、お気軽にご相談ください。現地チームとの共通認識づくりや前提条件の整理から、判断をスムーズに進めるお手伝いをします。
本サービスは、日本で最初の商用インターネットサービスプロバイダーとして誕生した IIJ グループと、AWS プレミアティアサービスパートナーであるサーバーワークスが共同で提供する「IIJ Managed Cloud for AWS」です。東南アジアを含むグローバル環境での利用にも対応し、現場の判断に寄り添った AWS 支援を行っています。
▶ 詳しい資料を確認する
▶ AWS活用の相談をしてみる
