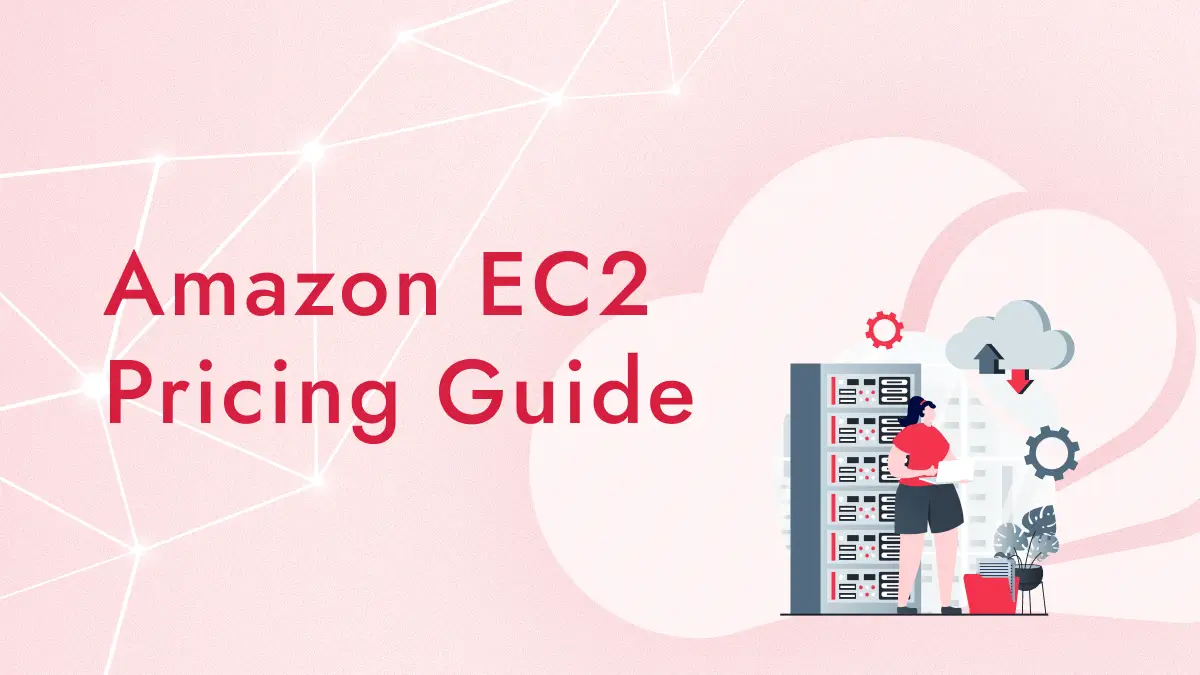
- Amazon EC2

老朽化したオンプレミスサーバの更新や、運用コスト削減を目的に「アマゾンウェブサービス(AWS)へのシステム移行」を検討する企業が増えています。
しかし、どの移行方式を選ぶべきか、どのツールを使えば安全に進められるのか、費用はどの程度かかるのか──実際に検討を始めると多くの疑問が浮かびます。
本記事では、オンプレミスや古い物理サーバをAWSへ移行する際に必要な手順や構成の考え方を、実務レベルで整理します。代表的な移行方法(リフト&シフト/リプラットフォーム)、主要ツール(AWS MGN・DMSなど)、費用感や注意点まで、AWS移行を初めて検討する方向けにわかりやすく解説します。
オンプレサーバをAWSへ移す取り組みは、単なるインフラ移設ではなく運用体制やコスト構造の見直しも含む取り替えに近い内容です。ここでは移行の目的と、検討時に押さえておくべき基本概念を整理します。
システムをAWSへ移す目的は、老朽化したハードウェア刷新に加え、保守作業の削減や障害耐性の向上が挙げられます。オンプレでは冗長構成やバックアップ環境の維持に手間が掛かりますが、AWSではマネージドサービスにより更新負担が減りやすい点が魅力です。
災害復旧の仕組みも標準化されており、可用性の底上げにつながります。改善余地がある運用基盤を継続するよりも、初期投資を抑えた設計に置き換えた方が、長期的に有利な選択になります。
AWS移行では、採用するクラウドサービスの層(IaaS・PaaS・SaaS)と、どこまで再設計するかを判断する考え方が必要です。既存環境をそのまま移す場合はリフト&シフト、AWSのマネージドサービスへ置き換える場合はリプラットフォームに該当します。
どちらの方式でも、移行後の運用コストや保守範囲が変わるため、目的に沿って方式を選びましょう。構成の最適化を考慮した計画を初期段階で固めておくと、後続工程の品質も安定します。
AWSへ移行する価値は、サーバ更新の負担軽減だけでなく、柔軟な拡張性やセキュリティ強化など複数の側面から得られます。ここでは移行後に得られる主要な利点を整理します。
オンプレ環境ではサーバ故障や部品交換に備える必要があり、保守計画と更新費が固定的に発生します。AWSではハードウェア管理を意識せずに運用できるため、設備の維持にかかる「人的・金銭的負担」が削減されます。
資産としてのサーバを所有し続ける必要がなくなり、更新サイクルに縛られない柔軟なシステム運用へ切り替えられます。
需要変動に合わせて「リソース容量を調整しやすい」点もAWSの利点です。急な処理増加にもAuto Scalingで追随しやすく、冗長化も複雑な構築作業なしで実現できます。また、複数のアベイラビリティゾーンを跨いだレイアウトにより、障害発生時の業務停止リスクも下がります。
AWSは暗号化・認証・監査ログなどのセキュリティ基盤が標準装備され、オンプレより「網羅的な仕組み」を構築しやすい環境です。S3やEBSスナップショットを使ったバックアップ整備も容易で、災害時の復旧シナリオにも落とし込みやすくなります。運用負荷を抑えながら備えを強化できる点は移行検討の大きな理由になります。
AWSでは利用量に応じた従量課金で支出構造が透明になり、過剰な設備投資を避けられます。さらに、リザーブドインスタンスやSavings Plansなど料金最適化の仕組みも用意されており、稼働実績に合わせたコスト設計が進めやすくなります。継続的な「利用状況の可視化」によって改善余地も把握しやすくなります。
AWSへの移行は場当たり的に進めると手戻りが増えやすいので、段階的に手順を整理して進めます。ここでは実務で一般的な進行ステップを順番に説明します。
最初に取り組む作業は、現行システムの正確な把握です。サーバ構成、利用中アプリケーション、データベース、ネットワーク接続、依存関係などを洗い出すことで、どこまでをAWSへ移すか判断できます。構成情報が不明確なまま進めると、後半で想定外のサービス停止につながるため、棚卸しの段階で抜け漏れを防ぐ視点が必要です。
移行方式は「どの程度AWSに合わせて構成を変えるか」によって異なります。既存構成を保ったまま移設するリフト&シフト、部分的にマネージドサービスへ置き換えるリプラットフォーム、アーキテクチャ全体を再設計するリアーキテクトが代表的です。システム規模や余力、将来の拡張性を踏まえて適した方式を選びます。
移行方式が定まったら、AWS側の基本構成を設計します。ネットワーク境界となるVPCの構成、認証と権限制御を司るIAM、運用を支える監視設定、バックアップポリシーなどをあらかじめ固めておく必要があります。ここでの設計精度が移行後の安定性やセキュリティ品質に直結します。
設計完了後は、実際にデータやアプリケーションをAWS側へ移します。ファイル領域はDataSync、サーバはAWS MGN、データベースはDMSなど、用途に応じた移行ツールを選ぶのが標準的なアプローチです。段階的なレプリケーションを活用することで、業務影響を抑えながら切り替えに備えられます。
移行直後に本番化せず、事前テストで構成や性能を確認します。本番切替時は切替手順とロールバック経路を整えてからスイッチを実施する運びになります。DNS切替のタイミングや監視設定の有効化を含めた多角的な確認が実稼働の安定につながります。
本番稼働が始まった後も、監視結果や負荷傾向を踏まえて構成を見直す工程があります。インスタンスタイプやスケール設計を調整し、Savings Plansなどの料金最適化も実施します。運用ルールや対応手順を整えることで移行効果を定着させられます。
AWSには、移行用途に合わせて複数の公式ツールが提供されています。ここではよく利用される4つのサービスを用途別に紹介します。
AWS Application Migration Service(MGN)は、オンプレミス上で稼働している物理サーバや仮想サーバをそのままAWSへ移す用途に向いています。
既存OSやアプリを変更せずレプリケーションする仕組みなので、本番稼働中でもダウンタイムを抑えながら移設できます。移行後に検証を挟んでから切り替える構成がとりやすく、初期フェーズで採用される割合が高いサービスです。
AWS Database Migration Service(DMS)は、データベースをオンライン移行する際に用いられます。
業務を止めずに移設できる継続レプリケーションに対応しており、移行元と移行先で構造が異なる場合でも補正しながら転送できます。OracleやSQL Server、MySQLからAuroraなどへの移行時に用いる場面が多く、DB切り替え時の停止時間を短くする手法として扱われます。
AWS DataSyncは、大容量ファイルやストレージの移転に適したサービスです。オンプレのNASやファイルサーバからS3やEFSへ直接転送でき、暗号化と圧縮を自動処理します。
帯域制御機能が備わっていて、業務トラフィックへ影響を与えず転送を継続できる点が特徴です。段階移行や夜間バッチ移行のシナリオにも適しています。
AWS Migration Hubは、移行プロジェクト全体を可視化するための統合管理サービスです。
MGNやDMSなど複数ツールを併用する場合でも、進捗状況を中央で把握できます。担当者が多い移行案件や長期プロジェクトで特に効果を発揮し、計画と実施を切り分けた運営管理を実現できます。
システム規模や要件によって、最適な移行方式や構成は変わります。ここでは代表的な4分類に分けて、移行の考え方と構成例を紹介します。
小規模システムの場合は、構成要素が少なく依存関係の整理が容易なため、比較的スムーズにクラウドへ移設できます。ファイルサーバであればS3やFSxを移行先に選び、権限管理をIAMで統合すると運用負担を抑えられます。社内向けのWebアプリはEC2へ載せ替えるだけで動作するパターンが多いですが、将来的にECSやサーバレスへ発展させる余地もあります。
販売管理や会計などの業務システムは、保守契約やライセンス構造を踏まえた段階的移転が求められます。まずは既存構成を維持したままリフト&シフトで安定稼働を確保し、その後に一部コンポーネントをマネージドサービスへ置き換える進め方が一般的です。監査ログやバックアップの標準化も並行して設計しておくと、移行後の運用が定着しやすくなります。
基幹系システムでは停⽌時間の短縮と可用性の維持が移設の優先事項になります。RDSやAuroraなどクラウドネイティブなDBへ移す場合はDMSによる段階移行が有効で、本番運用を維持しながら同期を継続する構成に適しています。大容量DBを扱う場合は、ストレージI/Oやリージョン構成も含めて事前検証を重ねることが成功への近道です。
Webアプリケーションは、AWSの強みが反映されやすい領域です。まずはロードバランサとAuto Scalingを組み込むことで、アクセス急増時の性能劣化を抑えやすくなります。WAFやCloudFrontも組み合わせるとセキュリティと配信最適化が両立できます。将来の拡張を見据えるならコンテナ化やサーバレス化へ移す設計を検討します。
AWSへの移行では、初期コストだけでなく移行後の月額費用や運用費用も含めて全体像を把握することが大切です。ここでは費用の内訳と、見積もり時に検討すべき観点を整理します。
初期費用には、「現状確認や環境設計」「PoC(検証)」「本番移設前の試験費用」などが含まれます。特に既存システムが複雑な場合や依存関係が読み取りづらい場合は、棚卸しの段階で一定の工数が発生します。物理サーバからの吸い上げはAWS MGNの導入作業が中心となり、データ量によって移設時間と作業費用が変わります。
稼働後に発生するランニング費用は、「コンピューティング・ストレージ・ネットワーク」の3要素が中心です。例えばEC2ではインスタンスタイプや稼働時間、S3ではデータ保管量とリクエスト数が費用に直結します。RDSもストレージ種別や冗長構成の内容によって料金が変わるため、負荷特性を踏まえたリソース割当が求められます。
AWS運用はオンプレと比較して柔軟でありつつ、適切な監視やセキュリティ設定が欠かせません。クラウド監視をCloudWatchに統一し、障害時の自動通知まで含めると、社内CSチームの作業負荷を削減できます。一方で、メンテナンスやセキュリティ改善には専門性が必要になるため、必要に応じて外部パートナーのサポート費用を含めるケースもあります。
AWSでは、移設直後はオンデマンド課金で様子を見て、稼働状況が安定してから予約型課金(RI/SP)へ切替える構成が一般的です。スケーリング機能でリソースを自動調整すれば、実際の利用状況に合わせた無駄のない運用が実現できます。料金計算の基盤が整った後にCost Explorerで全体を可視化すると、節減余地を見付けやすくなります。
AWSへの移行では、設計や手順自体が正しくても、事前準備や依存関係の把握が不十分なまま進めてしまうと稼働開始後に想定外のトラブルが発生します。ここでは実務で頻発するパターンと、その背景を解説します。
複数システムが連携する業務環境では、アプリケーションやバッチ処理の依存関係を洗い出さないまま移設へ進めると、切替後に通信途絶やデータ連携停止につながります。特にファイル連携や外部APIと結びついた設計では注意が必要です。早い段階で接続先や接続元を棚卸しし、段階移設の有無を見極めておくと安全です。
OSやミドルウェアのライセンス体系はクラウド化で変動する場合があります。Windows ServerやOracle DatabaseなどはBYOL前提かAWS提供ライセンスかで費用が異なり、誤った選定は割高課金へ直結します。事前に利用方式と提供元を整理し、クラウド対応可否を確認しておくことが欠かせません。
移行後の環境で起きやすい障害の多くはネットワーク関連です。通信要件やCIDR設計を見誤ると、接続不良やVPN帯域枯渇につながります。セキュリティグループとNACLの設定も合わせて確認し、移設検証で挙動を確認してから本番へ切り替える流れが安全です。
移行を完了することを優先し、稼働後の監視や運用整備が後回しになるケースがあります。本番切替後は、CloudWatchやAWS Backupを含めた運用計画を先に整備しておくと安定したクラウド運営につながります。運用整備と並行した移設計画を立てる構成が理想です。
AWSへの移行は、老朽化したオンプレサーバを更新するだけでなく、運用設計やコスト管理まで含めて刷新できる機会になります。移行を円滑に進めるには、現状の棚卸しを丁寧に進め、移設方式とAWS構成を照らし合わせながら段階的に検証する流れが適しています。移設後も監視や最適化を継続すると、スケーラビリティや可用性の面で長期的なメリットを得られます。
AWS の使い方、見積もり、構成、運用などで迷いや不安がある場合は、お気軽にご相談ください。現地チームとの共通認識づくりや前提条件の整理から、判断をスムーズに進めるお手伝いをします。
本サービスは、日本で最初の商用インターネットサービスプロバイダーとして誕生した IIJ グループと、AWS プレミアティアサービスパートナーであるサーバーワークスが共同で提供する「IIJ Managed Cloud for AWS」です。東南アジアを含むグローバル環境での利用にも対応し、現場の判断に寄り添った AWS 支援を行っています。
▶ 資料をダウンロードする
▶ お問い合わせはこちら
