
- ベトナム
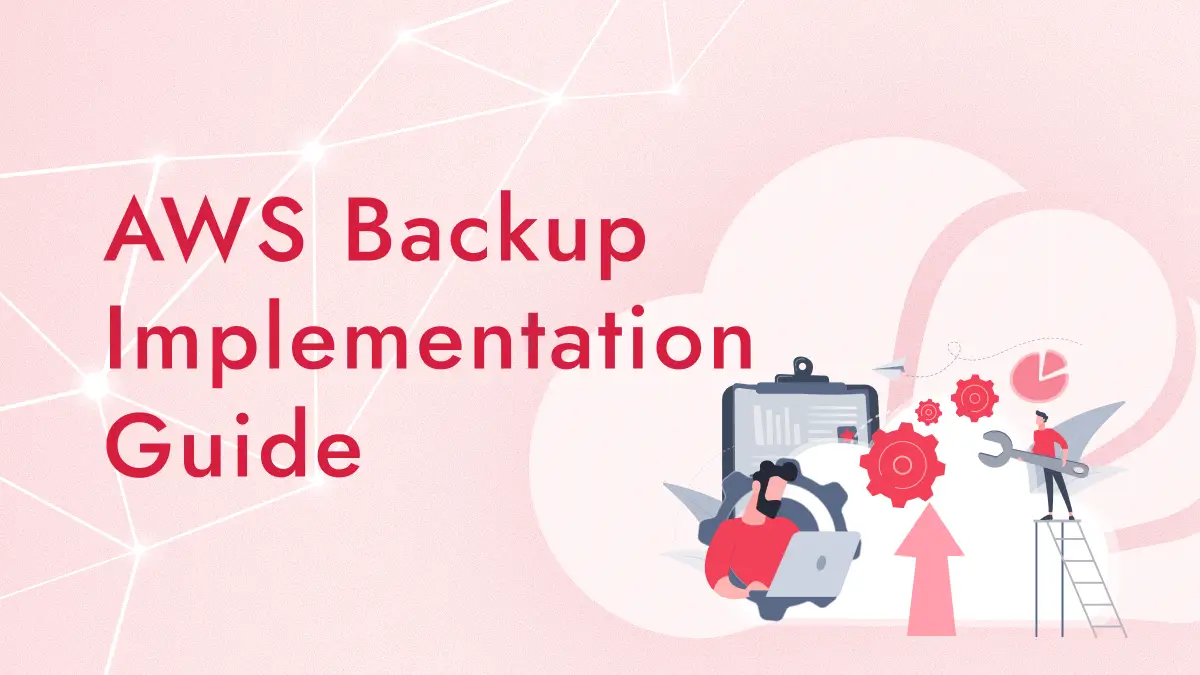
AWSでのバックアップ、サービスごとにバラバラで管理するのは面倒…。その課題を解決するのが AWS Backup です。本記事では、基本機能や対応サービス、設定方法から自動化の仕組み、運用で注意すべきポイントまでを解説。さらに見落としがちなコスト管理のコツも紹介します。
AWS Backupは、AWS上のさまざまなリソースを対象に、バックアップの取得・保存・復元を一元管理できるマネージドサービスです。個別サービスごとの設定を意識せずに、統一ポリシーで自動化・運用できる点が特徴です。
従来はサービスごとに異なる仕組みでバックアップを設定する必要がありましたが、AWS Backupを利用すれば統一的な管理ポリシーを適用できます。バックアップの取得・保存・復元までを一貫して扱えるため、運用チームの負担軽減とガバナンス強化に直結します。
AWS Backupの大きな特長は、マルチサービス対応による一元管理です。EC2やRDSといった主要サービスだけでなく、EFSやDynamoDBなども含めて統一ポリシーで管理できます。サービス横断でのバックアップ状況を可視化しやすくなり、運用ルールの徹底や監査対応も容易になります。その結果、セキュリティやコンプライアンス要件を満たす基盤づくりを効率的に進められます。
AWS Backupは、主要なコンピューティング・データベース・ストレージサービスを幅広くカバーしています。単一のポリシーでEC2やRDSといった基盤系リソースをまとめて管理できるため、個別にバックアップ設定を行う必要がありません。以下、代表的なサービスごとに特徴を整理します。
EC2インスタンスはEBSボリューム単位でバックアップを取得できます。スナップショット管理をAWS Backupに任せることで、世代管理や保存期間のルールを一元的に設定できます。
RDSやAuroraについては、データベースのスナップショット取得と復元を統合管理できます。マルチAZ構成や大規模データベース環境では、自動化により運用負荷を大幅に軽減できます。
NoSQLデータベースのDynamoDB、ファイルストレージのEFS、Windowsファイルサーバー互換のFSxなどもサポート対象です。ブロックストレージからデータベース、ファイルシステムまでをカバーでき、業務システム全体の保護を統一的に設計できます。
AWS Backupのアーキテクチャは、主に「バックアッププラン」と「Vault」の2つの要素で成り立っています。プランは運用ルールをまとめる単位、Vaultはデータを保存する領域という位置付けです。
AWS Backupでは、バックアッププランを起点に運用を設計します。プランには「いつ」「どのリソースを」「どこに」「どのくらいの期間」保存するかといったルールを定義できます。ルールにはスケジュールや保存先、ライフサイクルなどを細かく設定でき、これを複数のリソースに適用すると、サービス横断の統一的な管理が可能になります。
バックアップデータの保存先がBackup Vaultです。Vaultは暗号化やアクセス制御の単位となり、セキュリティを担保する役割を持ちます。IAMポリシーやVaultロック機能を組み合わせることで、誤削除や不正アクセスからバックアップを保護できます。運用上は「プラン=運用ルール」「Vault=保存先」と整理すると理解しやすいです。
AWS Backupの強みは、バックアップ運用を自動化できる点にあります。スケジュール設定やライフサイクル管理を組み合わせることで、人的なオペレーションを介さずに安定したバックアップが実現します。
バックアッププランのルールでは、Cron式や繰り返し指定でスケジュールを定義し、業務システムに合わせた定期的なバックアップを自動実行できます。たとえば「毎日深夜2時」「毎週日曜のメンテナンス時間帯」といった指定が可能で、人的オペレーションなしに安定して取得できます。
保存期間の自動管理(ライフサイクル管理)も設定できます。短期間は標準ストレージに保持し、一定期間が経過したら低コストのストレージクラスへ移行するといったルール化が可能です。「必要なデータは保持しつつ、不要に長期間保存してコストが膨らむ」といった事態を避けられます。
AWS Backupを利用するには、まずサービスを有効化し、初期設定を整えます。初期セットアップとIAM権限の調整が済めば、各リソースのバックアップを計画的に運用できるようになります。
AWSマネジメントコンソールにログインし、AWS Backupサービスにアクセスします。
「バックアップを開始」などのガイド付きフローに従って、利用するリージョンを指定します。
初回利用時にはデフォルトのVaultが自動作成されます。必要に応じて独自のVaultを追加できます。
AWS Backupは複数のサービスを横断して操作するため、IAMポリシーの設定が重要です。
AWSBackupServiceRolePolicyForBackup:バックアップ取得に必要
AWSBackupServiceRolePolicyForRestores:リストアに必要
権限不足のまま進めるとバックアップが失敗するため、専用ロールを作成し、最小権限でアタッチしておくのが推奨です。
「どのリソースを・いつ・どのように保存するか」を定義する設計図です。ここでルールを設定し、対象リソースを割り当てると、自動化されたバックアップが機能します。
バックアッププランを新規作成し、名前を付けます。
ルールを追加し、以下を設定します
バックアップ頻度(例:毎日、毎週)
開始時刻(例:深夜2時)
保存期間(例:30日)
保存先のVault
必要に応じてライフサイクル管理を有効化し、長期保存データを低コストストレージへ移行します。
バックアッププランを作成したら、対象となるAWSリソースを割り当てます。
EC2インスタンス → EBSボリューム単位で指定
RDS → インスタンス/クラスタを選択
DynamoDBやEFS → テーブルやファイルシステム単位で指定
複数リソースをまとめて同じプランに割り当てることで、統一ポリシー運用が可能になります。
プランを作成すると、自動スケジュールでバックアップが走りますが、手動で実行して動作確認するのも大切です。結果の成否をモニタリングする仕組みを整えておくと安心です。
AWS Backupコンソールから「バックアップを開始」を選択
対象リソースとVaultを指定
即時実行を確認し、完了するまで待機
バックアップジョブはコンソールやCloudWatch Logsでステータス確認が可能です。
成功:リソースがVaultに保存され、一覧に表示
失敗:IAM権限やVaultポリシーの不足が多い
また、CloudWatchメトリクスやSNS通知を組み合わせれば、失敗時に自動アラートを飛ばす仕組みも作れます。
バックアップの信頼性を確認するには、定期的な復元テストが不可欠です。AWS Backupではリソース種別ごとにリストア手順が用意されています。
Vaultから対象のスナップショットを選択
新規EBSボリュームを作成、または既存インスタンスにアタッチ
ネットワークやセキュリティグループ設定を見直し、動作を確認
スナップショットを選択して新規DBインスタンスを作成
必要に応じてパラメータグループやセキュリティ設定を再適用
本番環境へ切り替える前にテスト環境で検証
DynamoDB:テーブル名の競合に注意。新しいテーブルに復元するのが一般的
EFS/FSx:アクセス権やマウントポイントの再設定が必要
Aurora:クラスタ全体の復元になるため、部分的なリストアは不可
AWS Backupは設定や運用を誤ると、バックアップが正常に動作しないことがあります。以下、代表的なトラブル事例を紹介します。
バックアップ対象のリソースにアクセスできるIAM権限が不足していると、ジョブがエラーで終了します。専用ロールを作成し、必要なポリシーを付与しておく必要があります。
Vaultに対するアクセス許可が不足していると、バックアップデータは取得できてもリストアが実行できません。クロスアカウント利用や他リージョンへのリストア時はVaultポリシーを確認しておく必要があります。
本番業務が稼働している時間帯にバックアップを実行すると、リソース性能に影響する場合があります。業務時間外やメンテナンス時間に合わせたスケジューリングが推奨されます。
バックアップは「取れば安心」ですが、コスト面の管理を怠ると予想以上の請求につながることがあります。
バックアップデータはストレージに保存されるため、保存期間が長くなるほどコストが増加します。また、リージョンをまたぐコピーやリストアにはデータ転送コストが発生します。
ライフサイクル管理を設定していない場合、古い世代のバックアップが延々と残り続け、コストが膨らむケースがあります。定期的に保存状況を確認し、不要データを整理するのがよいでしょう。
ストレージクラス選定:長期保存は低コストクラスへ移行
バックアップ頻度:業務要件に応じて最適化(例:日次ではなく週次に落とす)
保存期間の見直し:法規制や業務要件に合わせて最小限に設定
すべてのリソースを無条件にバックアップするとコストが膨らみ、管理も煩雑になります。まずは業務に直結するシステムや法規制上の保管が必要なデータを優先対象とし、一時利用の検証環境やキャッシュデータなどは対象外とする線引きを行いましょう。
バックアップが正常に取得されても、リストアが失敗すれば意味がありません。年次や四半期ごとにテスト環境で復元を実行し、データの完全性や手順の妥当性を確認することをお勧めします。
AWS Backupのライフサイクル機能を活用し、保存期間に応じてストレージクラスを切り替えることでコストを抑えられます。たとえば「30日間は標準ストレージ」「それ以降は低コストストレージに移行」といった運用を取り入れると効果的です。
CloudWatchメトリクスやSNS通知を組み合わせ、バックアップジョブの成否をリアルタイムに監視しましょう。失敗時に即座にアラートを受け取れる仕組みを作ることで、復旧までの時間を短縮し、業務影響を最小限に抑えられます。
AWS Backupは、EC2やRDSをはじめ複数サービスを一元的に管理し、バックアップを自動化できるマネージドサービスです。運用を誤るとコスト増やリストア失敗といったリスクもありますが、対象範囲の整理や定期的なリストアテストを行えば安定した運用が可能です。導入により、バックアップ業務の効率化だけでなく、事業継続性やセキュリティ強化にも直結します。
